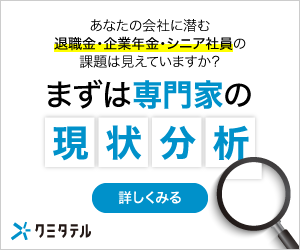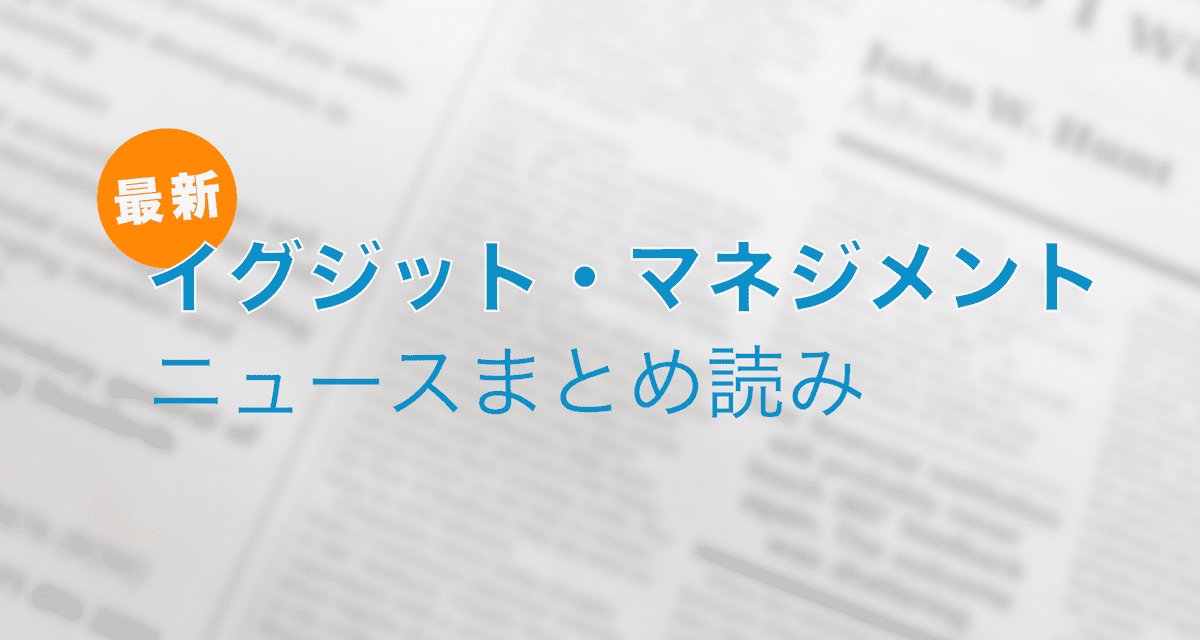「骨太の方針2023」から読み解く退職金課税の行方

先日閣議決定された2023年度の骨太の方針に「退職所得課税制度の見直し」が盛り込まれました。これを受けて、退職金に対する課税の強化を匂わせるような報道もありますが、実際どのような見直しが想定されるのか、解説します。
現在の退職金課税の仕組み
まず、今の退職金課税の仕組みがどうなっているかを簡単に説明します。退職金は一般の会社員にとっては人生で一番高額な収入になります。もちろん中には「うちの会社には退職金なんてないよ」という方もいらっしゃいますが(実は今の私もそうですが)、大企業を定年退職すると退職金の総額が2,000万円を超えるのは決して珍しいことではありません。
これをもし給与や賞与と同じ扱いで課税すると、税率が非常に高くなって手取りが大きく減ってしまいます。しかし退職金には「給与の後払い」や「老後の生活費」の確保という意味合いもあるため、この点を考慮して税負担を軽減する仕組みが3つ設けられています。
1つ目は、勤続年数に応じた「退職所得控除」です。退職金は基本的に勤続年数が長くなるほど増えていきますが、そのうち1年あたり40万円は課税の対象外となります。
例えば勤続10年で退職した場合、40万円×10年で400万円までは非課税、20年なら800万円(=40万円×20年)までは非課税で、それを超えた部分にだけ税金がかかります。
そして勤続20年を超えると、この非課税枠が1年あたり40万円から70万円に拡大します。例えば勤続30年で退職すると、最初の20年分で800万円、最後の10年分で70万円×10年=700万円、合計1500万円までの退職金には税金がかかりません。勤続40年だと後半20年分で1400万円(=70万円×20年)となり、合計2200万円(=800万円+1400万円)までは税金がかからないことになります。
2つ目は「1/2課税」という仕組みです。退職金が1点目の退職所得控除の額を超えた部分には税金がかかりますが、その全部に税金をかけるのではなくて、半分にしたうえで税金を計算します。
例えば勤続20年で退職金が1000万円の場合、退職所得控除額800万円を差し引いた残り200万円が課税対象になりますが、これを半分の100万円にしてから税率をかけて税額を計算します。
3つ目は「分離課税」という仕組みです。給与収入などは他の収入と合算したうえで税率を適用する「総合課税」の方式がとられており、他の収入で金額が大きくなると税率が高くなって税負担が重くなります。
これに対して、退職金は「退職所得」として別個に税額を計算するため、退職金以外の収入があったとしても税負担には影響しません。
見直しの目的は「労働移動の円滑化」
このように、退職金には税金面での3つの優遇がありますが、このうち今回の見直しの対象となっているのが1つ目の退職所得控除です。同じ会社にずっと勤めた場合、20年を超えると1年あたりの控除額が40万円から70万円に拡大しますが、途中で転職してしまうと勤続年数がリセットされてこの恩恵を受けることができません。
この仕組みが転職を思いとどまらせる要因となり、ひいては成長分野への労働移動の円滑化を阻害しているのではないか、ということで、今回の骨太方針に見直しが盛り込まれました。
ただ、この部分の見直しが労働移動の円滑化にすぐに結びつくかというと、あまり期待できないと言わざるを得ません。退職金に関しては、そもそも各企業で定めている支給基準が転職に不利なケースもまだまだ多いため、そうした点も含めて変わっていかなければ、実現は難しいでしょう。
【関連コラム】 自己都合なら退職金を減らしても問題ないのか
そうはいっても、今の退職所得控除の段差は転職者に不利であることに変わりはないため、見直し自体は正しい方向性だといえます。では具体的にどのような見直しが行われようとしているのでしょうか。
想定される退職金課税の見直し内容
これに関しては、骨太方針にも関連文書にもまだ具体的な言及はないため、確かなことはわかりません。ただ今回の見直しの趣旨からすると、退職所得控除の1年あたり額を、勤続年数にかかわらず一定にすることが、まず考えられます。
これはあくまで仮定ですが、例えば退職所得控除額を勤続1年につき一律50万円とした場合、以下のように勤続30年未満では今よりも控除額が大きくなって有利に、30年を超えると逆に控除額が小さくなって不利になります。

ただし、いきなり算定方法を切り変えてしまうと、見直しのタイミングで個人の生活設計や退職行動に大きな影響を与えかねませんので、仮に控除額の見直しを行う場合でも、すぐには大きな影響が出ないような措置が取られるものと考えられます。
もう1つ考えられる見直しの内容として、勤続年数の通算があります。実は、企業年金や個人型確定拠出年金(iDeCo)には既にこの仕組みがあります。転職した場合でもその時には給付を受け取らずに相互に他の制度に資産を移し、積み立てを継続する「ポータビリティ」が整備されています。
そして、最終的に積み立てられた資産を一括でまとめて受け取ったときには、原則として退職所得の扱いとなり、その際の退職所得控除額は転職前の期間が通算されます。ですから、転職による税金面での不利益を回避することができます。
これに対して、会社から直接支給された退職一時金を企業年金制度などに移すことは、現状認められていません。もしこれが認められれば、資産を移すことによって勤続年数を通算し、転職による不利益を解消することが可能となります。加えて、老後に向けた資産形成にも寄与することが期待されます。
さらに、退職金課税の見直しは、企業年金やiDeCoといった私的年金税制の見直しにも波及する可能性があります。
詳細はここでは割愛しますが、私的年金の分野では、年金受取の場合と一時金受取の場合での税負担の違いや、特別法人税の存在が以前から課題として指摘されています。しかしながら、実際にはなかなか検討が進みませんでした。今回、退職金課税の大きな見直しが取り上げられたことで、私的年金の税制についても包括的な見直しが行われる可能性があり、この点についても注目されます。
以上、今回は退職金課税の行方について解説しましたが、このテーマに関しては様々なメディアで取り上げられており、中には不安を煽るような不確かな情報も散見されます。見直し内容が確定してからでも決して遅くはないので、自分や、自社の社員に当てはめたときに実際どのように影響するのか、正確な情報に基づいてしっかり見極めるようにしましょう。
著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長
1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。