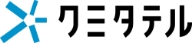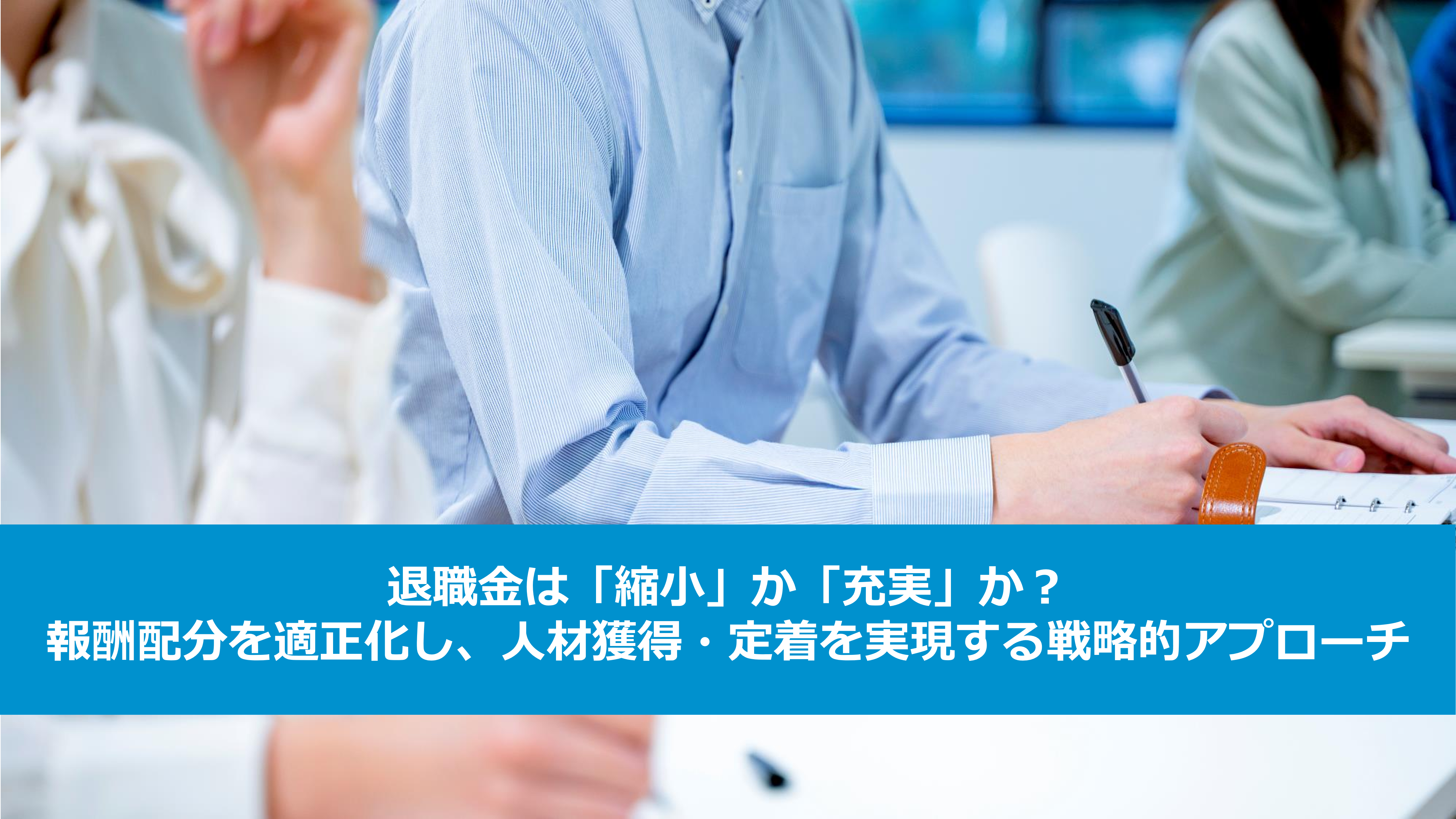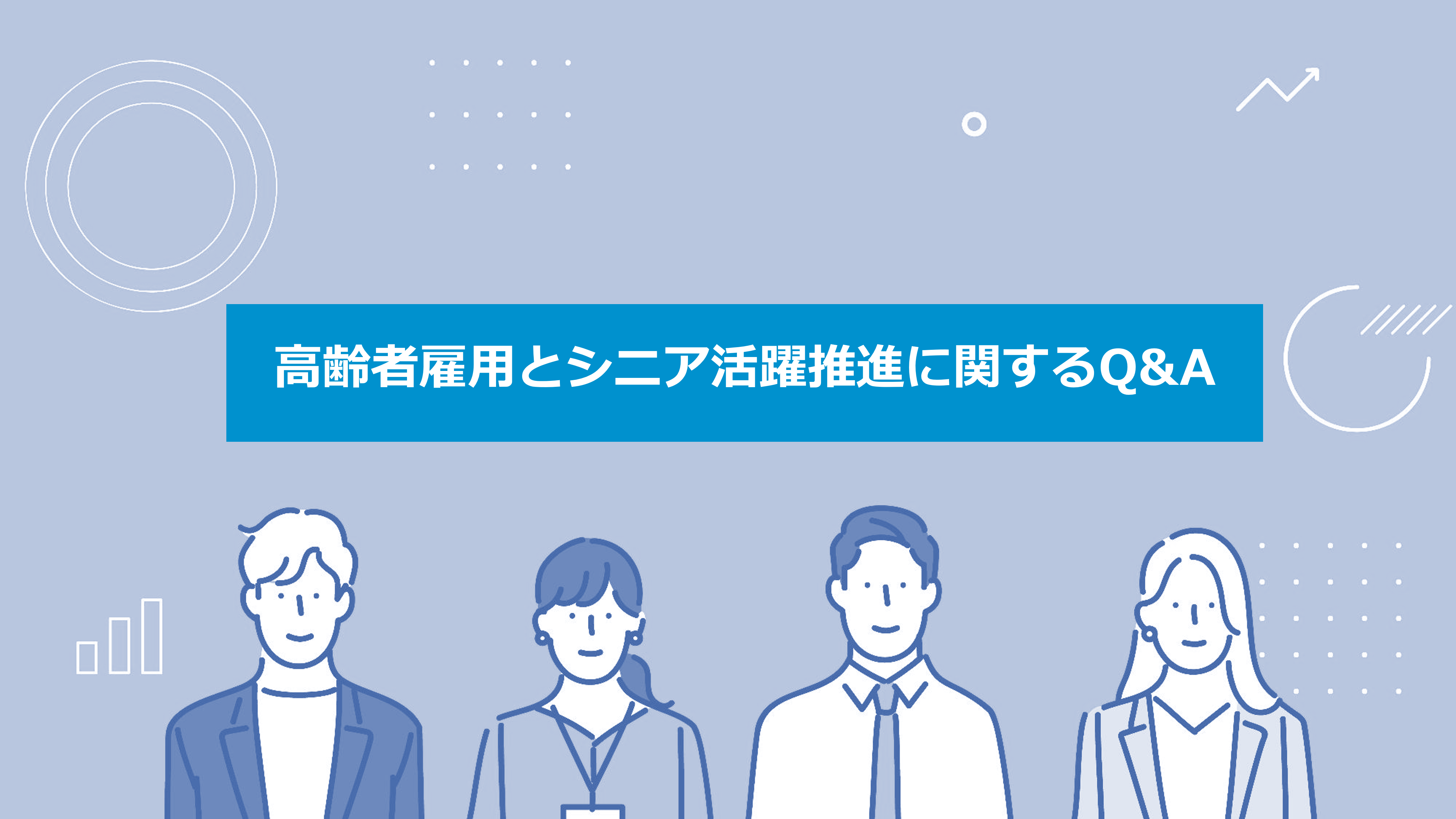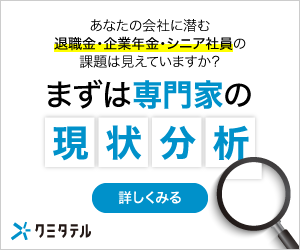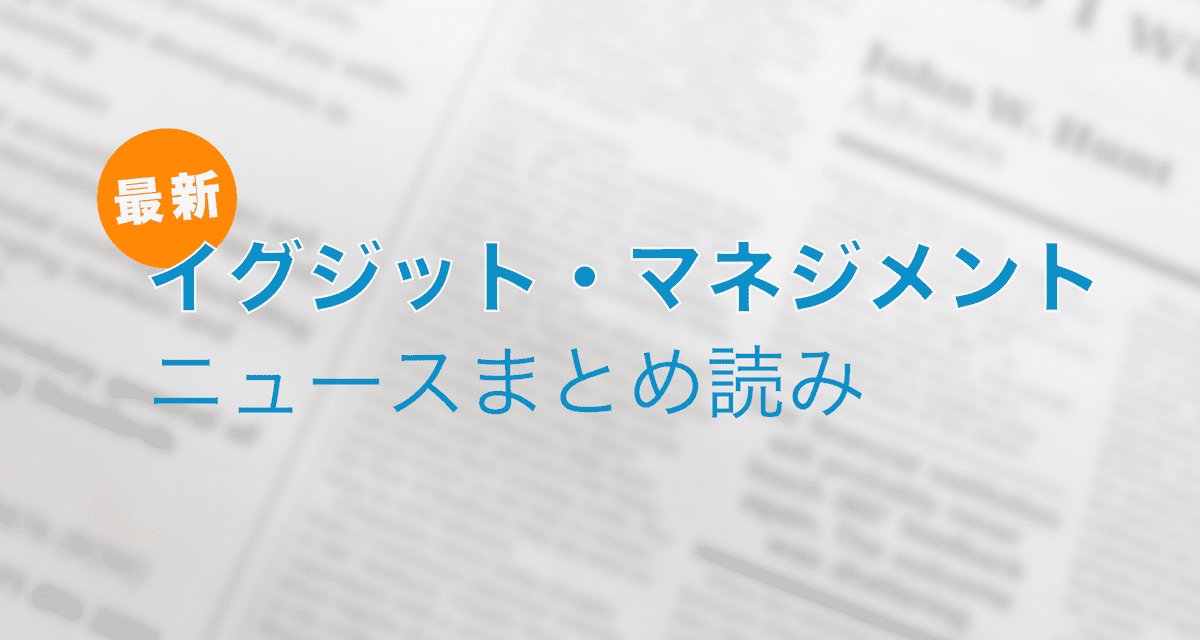「ただの雇用延長」で終わらせない。シニア社員を輝かせるイグジット・マネジメント発想の「新・高年齢者雇用制度」

改正高年齢者雇用安定法への対応が迫られ、多くの企業が定年後再雇用や定年延長制度を整備しています。しかし、その実態は「法律で決まったから、とりあえず65歳まで働いてもらう」という、場当たり的な運用に陥ってはいないでしょうか。
その結果、現場では様々な“歪み”が生じています。再雇用されたシニア社員自身のモチベーションは上がらず、処遇と役割のアンバランスに本人も周囲も不満を抱える。そして何より、そうしたシニアの姿を見た若手・中堅社員が、自社の将来に希望を持てず、エンゲージメントを下げてしまう。これでは、制度が組織の「停滞」を加速させているようなものです。
これらの課題の根本原因は、制度に「出口戦略」、すなわちキャリアの完成を見据えた思想がないことにあります。本記事では、この根深い問題を「企業の活力」に転換する鍵として、イグジット・マネジメントの発想に基づいた、まったく新しい高年齢者雇用制度の設計方法を解説します。
なぜ従来の再雇用制度は「停滞」を生むのか?
多くの企業で定年後再雇用制度が機能不全に陥るのは、単なる制度設計の不備という表面的な問題ではありません。その根底には、日本の雇用慣行に根差した、3つの根深い構造的欠陥が存在します。
一つ目は「出口」不在の“足し算”思考です。
高年法改正から作られてきた多くの再雇用制度は、60歳という節目に、ただ「5年」や「10年」という時間を足し算しているに過ぎません。その先に、従業員の「キャリアの集大成」というゴール(出口)が描かれていないのです。
従業員視点でみるとこれまでの会社人生では、「定年」という一つの大きなゴールがありました。しかし、そのゴールを通過した先に新たな目標が設定されるはずが、されない。その為、日々の業務は「キャリアの集大成」というゴールに向かうための意義ある活動ではなく、ただ時間をやり過ごすための作業へとその意味合いを変えてしまいます。ゴールのないキャリア延長は、本人のモチベーション低下を招くのは当然と言えます。
二つ目は、役割と貢献の“再定義”の欠如です。
多くのケースで、60歳以降の役割や貢献の形が曖昧なまま、処遇だけが引き下げられます。現役時代と同じような働きを期待されても、給与が下がれば意欲は湧きません。逆に、「いてもらうだけ」の閑職を与えられれば、長年培ってきたプライドは深く傷つきます。彼らが持つ経験や知恵という最も価値ある資産を、戦略的に活用できていないのです。
三つ目は、本人まかせの“マインドセット”です。
最も根深いのがマインドセットの問題です。多くの日本企業は、長年にわたり終身雇用や年功序列というシステムの中で、従業員に「キャリアは会社が用意するもの」という意識を植え付けてきました。会社への忠誠心と引き換えに、キャリアの舵取りを会社に委ねる文化を醸成してきたのです。
その会社が、60歳を過ぎた途端に、手のひらを返したように「さあ、今日から自律的に考えてください」と求めるのは、あまりにも酷な話です。それは、本人にとって「梯子を外された」ようなものであり、何をどう考えれば良いのか分からず、戸惑いと不安に陥るだけです。キャリアのオーナーシップが本人にないまま年を重ねてしまったとすれば、それは本人の資質以上に、会社自身のこれまでの仕組みの問題でもあります。
この「依存のマインドセット」を「自律のマインドセット」へと転換させる支援を抜きにして、本人の意識改革だけを期待しても、事態は決して好転しません。
イグジット・マネジメントで創る「戦略的セカンドキャリア制度」
では、どうすればシニア社員を「お荷物」ではなく「お宝」へと転換できるのでしょうか。イグジット・マネジメントの思想に基づき、制度を根本から再設計する3つのポイントをご紹介します。
ポイント1 50代から「キャリアの棚卸し」を始める
変革は60歳直前では手遅れです。50代を「セカンドキャリアへの助走期間」と明確に位置づけ、全ての従業員にキャリアデザイン研修や専門家との面談機会を提供します。
自身の経験やスキルを棚卸しし、「この会社で、そして社会で、自分は何を価値として貢献できるのか」を考えるプロセスを、会社が全面的に支援します。
ポイント2 「貢献の形」を多様化し、再契約する
60歳以降の貢献の形を、画一的ではなく、本人の希望と適性に応じて複数用意します。そして、その役割とミッションを明確に定義した上で、貢献度に基づいた処遇を決定し、「新たな契約」を結び直すのです。
【コースの例示】
A) 技能伝承・メンターコース: 後進の育成や、暗黙知の形式知化に特化する。
B) 専門職・プロフェッショナルコース: 高度な専門性を活かし、特定のプロジェクトや難易度の高い課題解決を担う。
C) 新領域チャレンジコース: 社内ベンチャーや社会貢献活動など、新たな分野で人脈や経験を活かす。
ポイント3 「リスペクト」を醸成する文化作り
残念ながら制度を整えるだけでは不十分です。シニア社員の貢献を全社で称え、可視化する場(社内報での特集、アワードの創設など)を設けることが重要です。また、彼らが持つ知見を若手が敬意をもって学べる勉強会などを企画し、「尊敬されるシニア」と「彼らから学ぶ若手」というポジティブな関係性を意図的に創り出します。
* * *
高年齢者雇用制度は、法律で定められた義務や、守りのコストセンターではありません。それは、企業の競争力を根幹から高めるための、極めて戦略的な投資機会です。
イグジット・マネジメントに基づいて設計された制度は、シニア社員一人ひとりを輝かせるだけにとどまりません。その「尊敬されるシニアの姿」は、後に続く若手・中堅社員にとって最高のロールモデルとなり、「この会社で働き続ければ、自分もあんな風にキャリアの集大成を迎えられる」という希望と信頼を育みます。それこそが、組織全体のエンゲージメントを高め、持続的な成長を実現する、何物にも代えがたい原動力となります。
著者 : 八丁宏志 (はっちょうこうじ)

クミタテル株式会社 取締役
1979年生まれ。専門学校卒業後、システム開発会社を経てIICパートナーズ入社。社内インフラの整備・運用からソフトウェアの開発・保守を手掛け、退職金・企業年金のコンサルティングにも従事。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに取締役に就任。人数規模、業種業態を問わず退職金制度を中心としたコンサルティングサービスを提供。