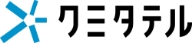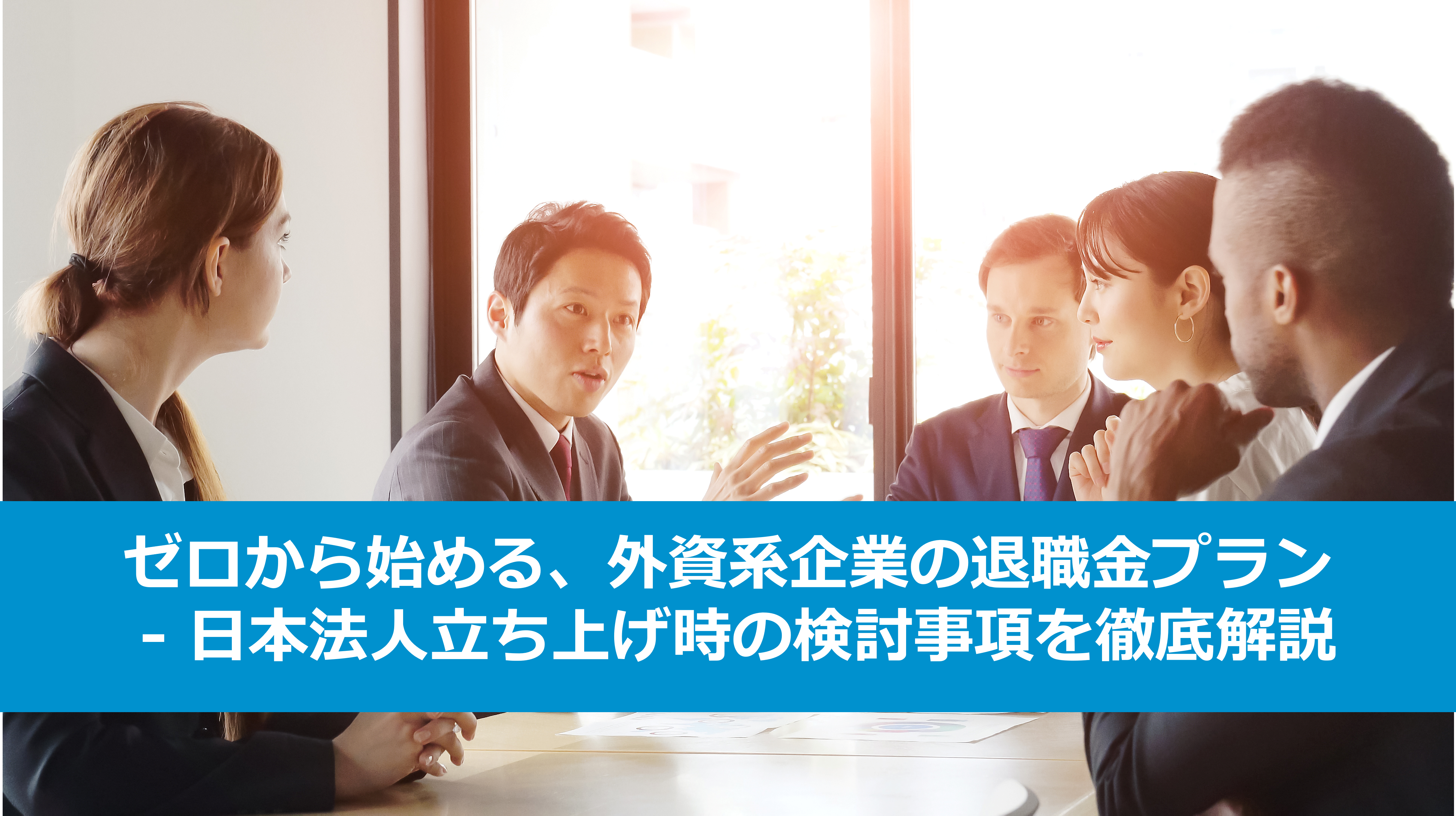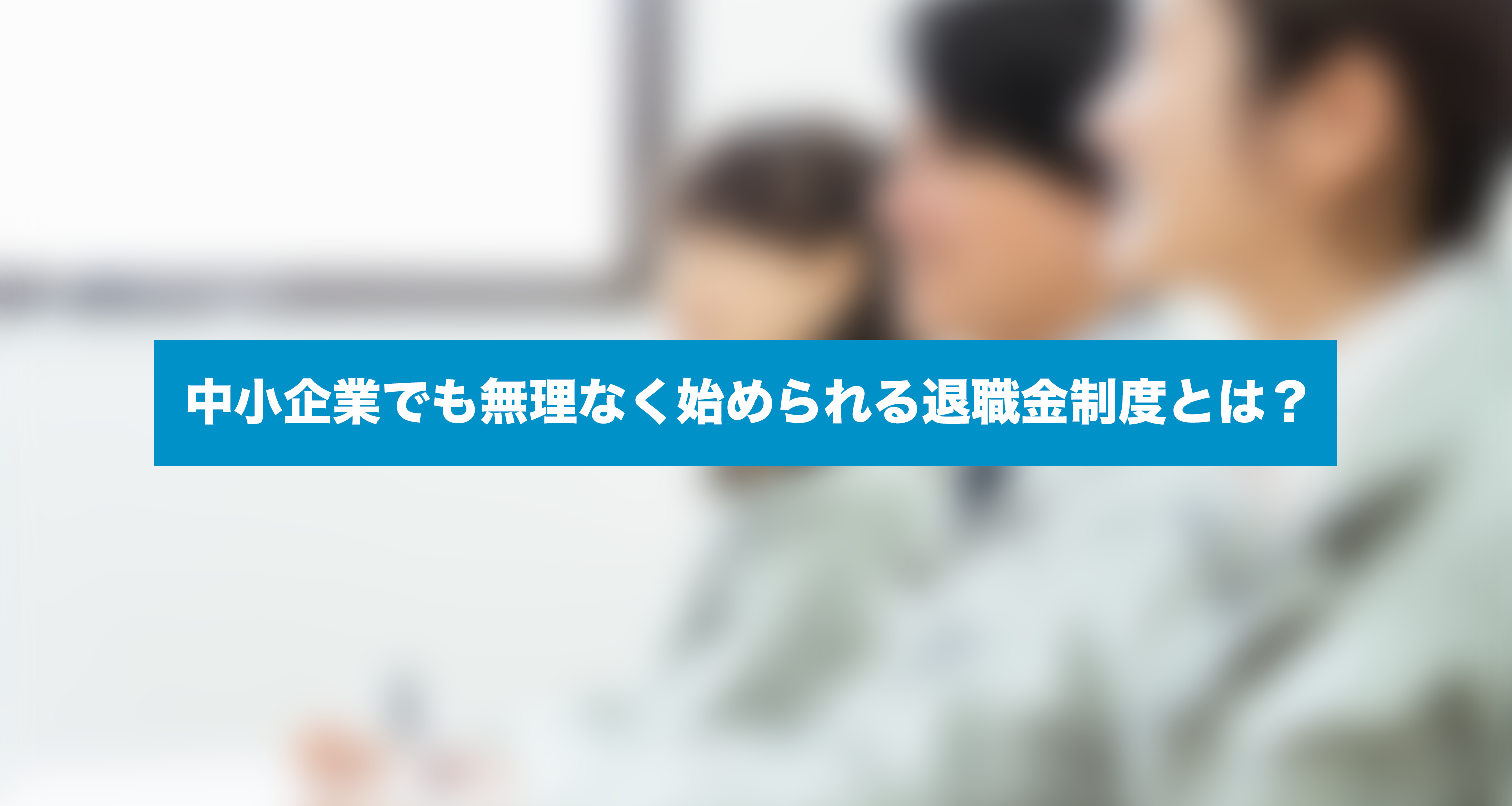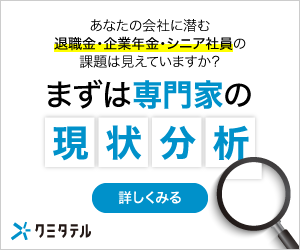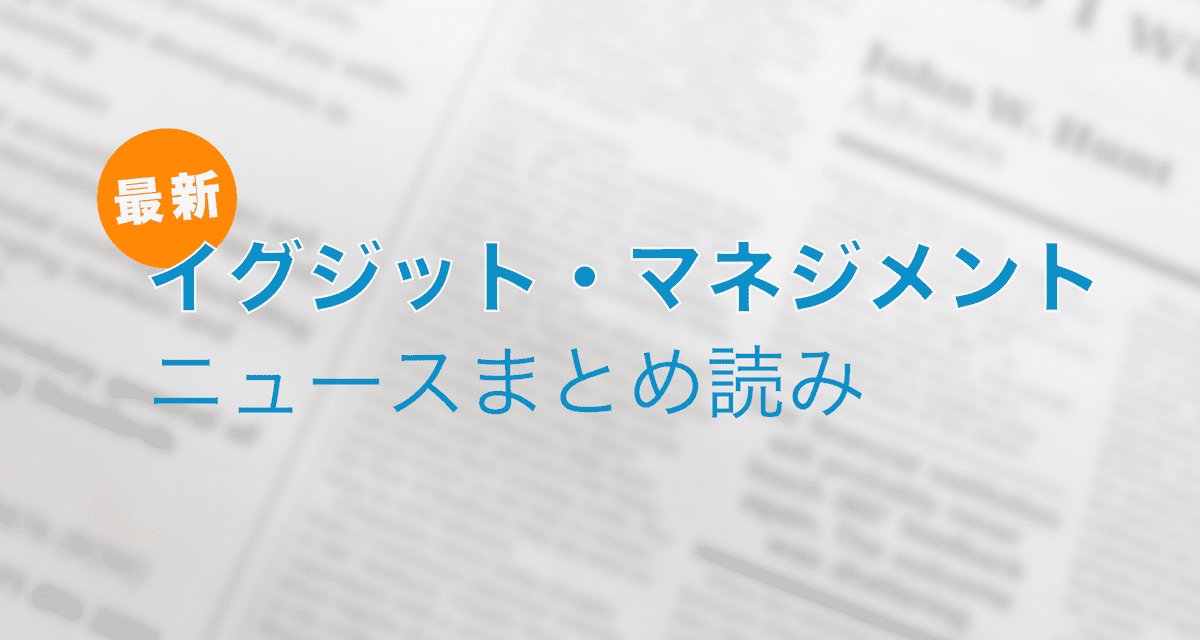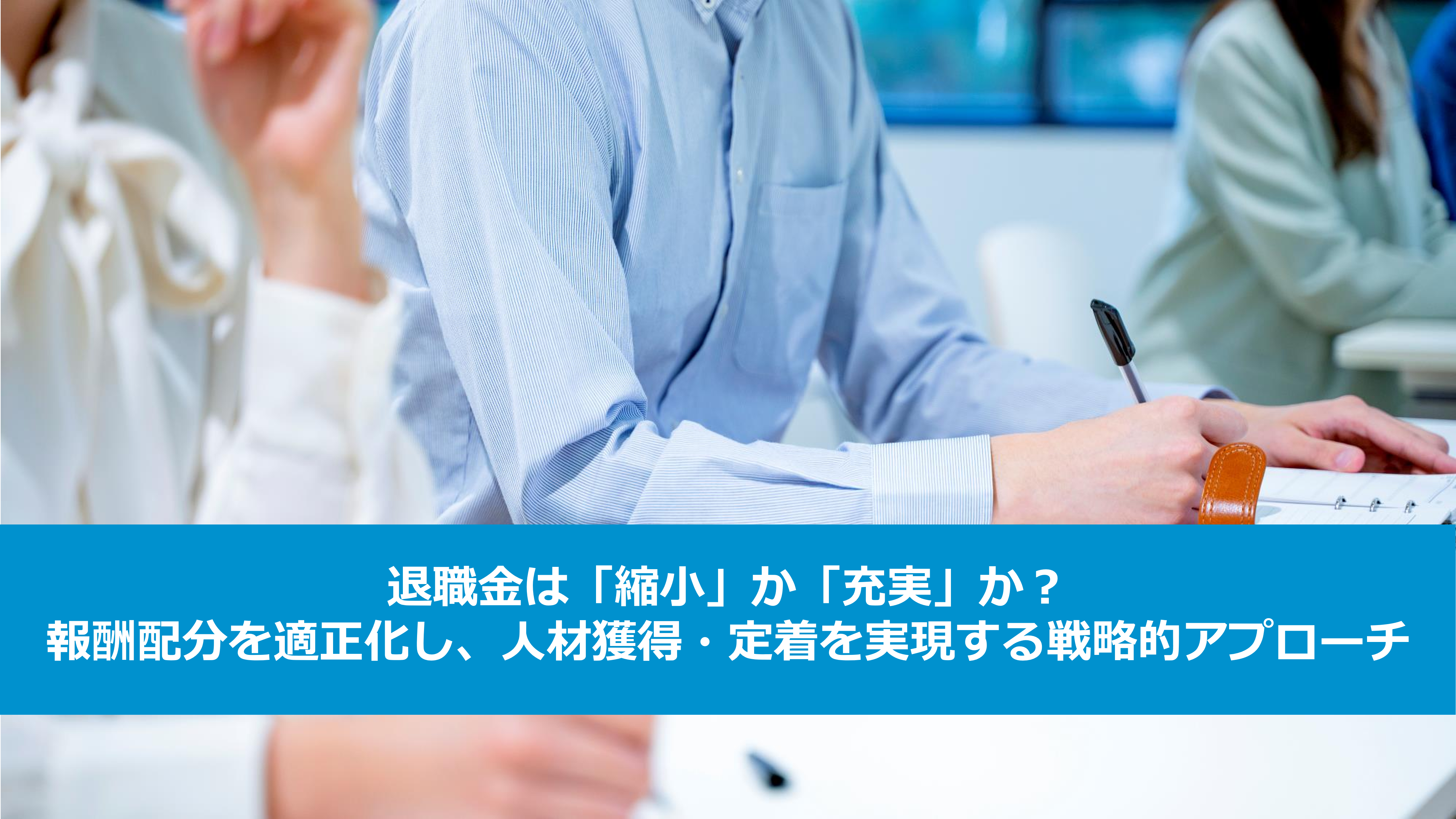人材は「定着」させるな? 逆転の発想で組織を活性化する「雇用とキャリアの出口戦略」
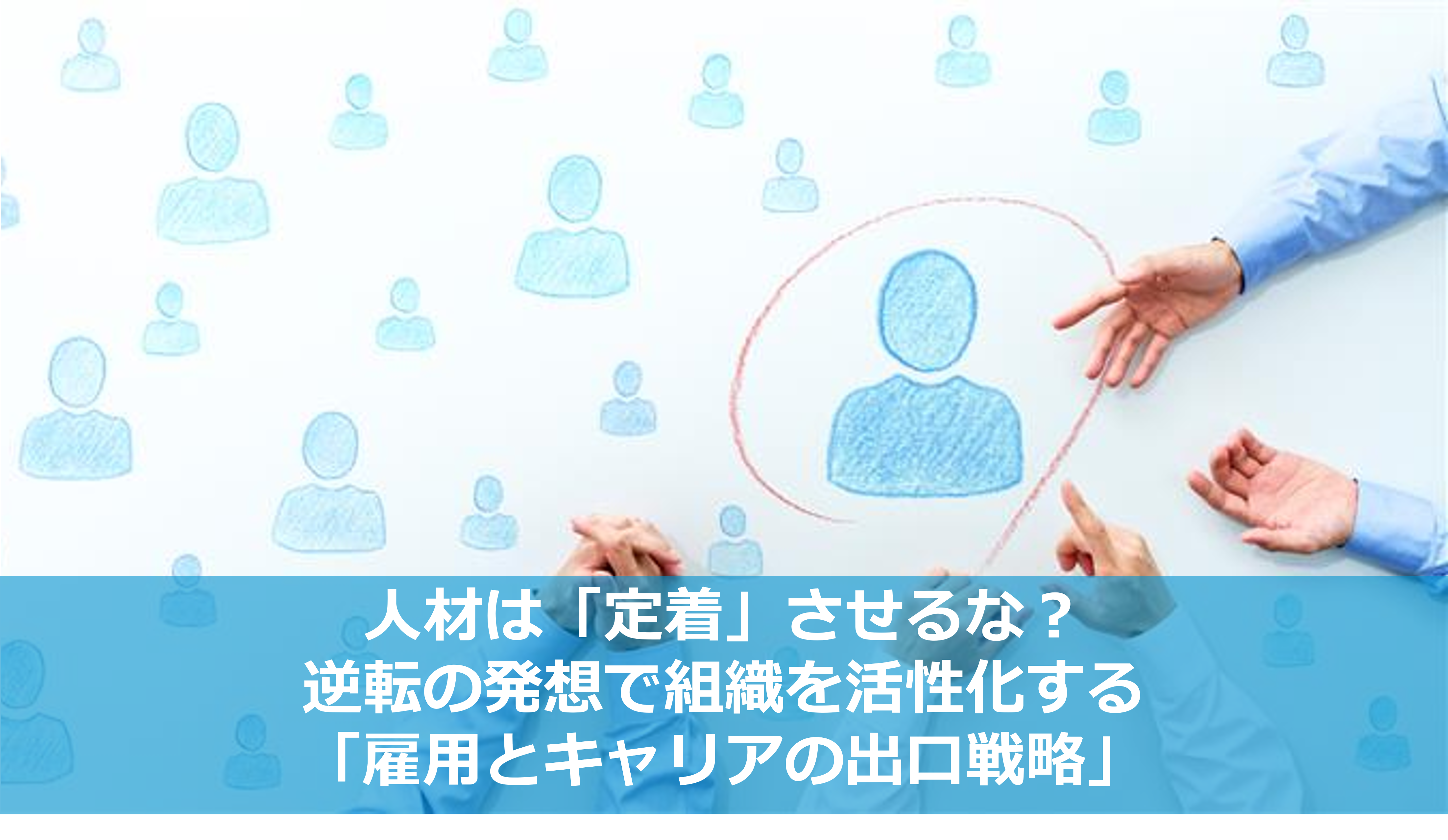
2021年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、企業は70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。かつて日本の多くの企業にとって、60歳定年は従業員の「出口」が自動的に決まる、ある意味で管理しやすい仕組みでした。
しかし今、その前提は完全に崩れ去り、企業は従業員のキャリアの終え方、すなわち「退職の在り方」そのものを、否応なく見直しなければならない時代に突入しています。
高年齢者層の雇用が長期化し、組織の「出口」が目詰まりを起こしやすくなる一方、深刻な人手不足を背景に、多くの企業は若手、中堅の流出を防ぐためのリテンション(定着)施策に躍起になっています。
しかし、この「出口の目詰まり」と「必死の引き留め」という組み合わせが、皮肉なジレンマを生んでいるのです。結果として、本当に意欲のある優秀な人材は成長機会を求めて外部に流出し、一方で変化を望まない従業員ばかりが社内に滞留してしまう。そんな“代謝不全”に悩まされてはいないでしょうか。
もし、そのジレンマの根本原因が「定着」という思想そのものにあるとしたら?
「従業員の退社」を、管理上の失敗やコストではなく、組織が健全に成長するための戦略的な機会として捉え直すことができたとしたら?
そこで私たちが提唱するのが、逆転の発想から生まれる「雇用とキャリアの出口戦略」、すなわち『イグジット・マネジメント』です。これは、従業員の「出口(退社)」を起点に、自律、定着、育成、採用という全てのプロセスを再設計し、個人と組織の双方にとってポジティブな循環を生み出す、まったく新しい人事戦略上の概念です。
前置きが長くなりましたが、本コラムでは、この「イグジット・マネジメント」が、なぜ今の時代に不可欠なのか、経営や人事上のメリットについて解説します。
イグジット・マネジメントの概念
それでは、本稿のキーワードである「イグジット・マネジメント」とは、具体的に何を指すのでしょうか。それは単なる退職手続きの改善や、アルムナイネットワークの構築といった個別施策を意味する言葉ではありません。
イグジット・マネジメントの本質とは、従業員の「退社」を、組織と個人の成長サイクルにおける最も重要な起点と定め、そこから逆算して人事のあらゆる機能(自律、定着、育成、採用)を戦略的に再構築していく概念です。
これまで多くの企業は、「従業員は自社の“資産”であり、流出を防ぐべき」という所有の思想に基づいていました。
しかし、キャリア観が多様化し、個人が会社に依存せず自律的にキャリアを形成する時代において、この考え方はもはや機能しません。イグジット・マネジメントは、会社と従業員の関係を「所有」から「期間限定のパートナーシップ」へと捉え直します。
企業は従業員の市場価値向上にコミットし、従業員は在籍期間中の貢献にコミットする。だからこそ、パートナーシップの終わりである「退社」は、互いへの感謝と共に、次のステージへとつながるポジティブな門出であるべきです。
この思想を具現化するのが、最大の特徴である「逆算のアプローチ」です。
まず初めに「我が社にとって理想の退社とは何か?」を定義します。例えばそれは、「従業員が在籍中に得たスキルと経験に自信を持ち、次のキャリアへ円満に旅立ち、退職後も自社のファンであり続けてくれる状態」かもしれませんし、「従業員が新卒で入社し、定年までたゆまずに努力を続け、貢献した後、定年後のセカンドキャリアを歩む状態」かもしれません。
この理想の出口を定めることで初めて、「その状態に至るために、従業員にはどのような『自律』を促すべきか」「自律を促す『定着』環境とは何か」「そのために必要な『育成』プログラムは何か」、そして「この価値観に共鳴する人材をどう『採用』すべきか」という問いへの答えが、一本の線として明確につながるのです。
つまり、これは組織の「新陳代謝」をデザインすることに他なりません。出口が健全に機能してこそ、新しい血が巡り、組織は常に活性化され、環境変化への適応力を維持できます。「定着」という名の“淀み”を意図的に手放し、清らかな“流れ”を創り出す。それこそが、イグジット・マネジメントが目指す、企業の持続的な成長の姿です。
イグジット・マネジメントがもたらす経営上のメリット
イグジット・マネジメントは、単なる人事の新しい考え方にとどまらず、企業経営そのものに具体的かつ強力なメリットをもたらします。これまで述べてきた「逆算のアプローチ」が、最終的にどのような経営価値に結びつくのか、4つの視点から解説します。
第一に、「組織の健全な新陳代謝をデザインし、硬直化を防ぐ」という点です。
ここで言う新陳代謝とは、必ずしも中途退職による人材の入れ替えだけを意味しません。イグジット・マネジメントが目指すのは、従業員一人ひとりが自律的なキャリアを歩むことであり、その形は様々です。
ある従業員は成長の過程で新たな挑戦の場を外部に求めるかもしれません。また別の従業員は、会社の中で長く価値を発揮・成長し続け、定年などを機に、培った経験を活かして充実したセカンドキャリアへと円満に巣立っていくかもしれません。
重要なのは、この両様の「ポジティブな出口」が戦略的にデザインされていることです。従業員のキャリアの最終着地点が明確であるからこそ、組織は常に活性化され、旧来のやり方に固執することなく、しなやかで強い体質を維持することができます。
第二に、「採用ブランディングの強化」です。
「あの会社でキャリアを築けば、市場価値の高いプロフェッショナルになれる」という評判は、最高の求人広告です。そして、その評判を証明するのは、外部で活躍する卒業生だけではありません。社内で長期にわたり専門性を高めて貢献し、充実したセカンドキャリアへと巣立っていく定年退職者の姿もまた、「この会社は個人のキャリアを長期的に支えてくれる」という強力な証しとなります。この両面からの信頼性が、成長意欲の高い優秀な人材を惹きつけるのです。
第三に、「アルムナイ(卒業生)という最強の無形資産の形成」です。
ここで言うアルムナイとは、若くして転職した元従業員に限りません。長年の貢献を経て円満に定年退職した大先輩たちもまた、会社にとってかけがえのないアルムナイです。彼らは、ビジネスやカルチャーを誰よりも深く理解した「応援団」であり、その豊富な知見や人脈は、将来の優良顧客やビジネスパートナー、あるいは若手へのメンターなど、計り知れない価値を持つ経営資産となり得ます。
そして最後に「従業員エンゲージメントの質の向上」です。
「この会社は、私のキャリアの最終着地点まで真剣に考えてくれている」という信頼感は、従業員に絶大な心理的安全性をもたらします。キャリアを会社に縛られているという閉塞感から解放され、自律的にキャリアプランを描けるからこそ、従業員は安心して目の前の仕事に挑戦し、プロフェッショナルとして誇りを持って貢献しようという意欲が湧くのです。これは、会社への“しがみつき”ではなく、未来への希望に根差した、本質的なエンゲージメントと言えるでしょう。
このように、イグジット・マネジメントは、組織の活力を引き出し、採用力を高め、新たな事業機会を創出し、従業員の意欲を向上させる、極めて合理的な経営戦略なのです。
* * *
これからの企業経営における人事戦略の「イグジット・マネジメント」という概念をご紹介しました。もはや、従業員の離職を単なる「コスト」や「失敗」と捉え、定着率の維持に固執する時代は終わりを告げようとしています。
これからは、従業員の「出口」を、組織と個人の双方にとっての「未来への投資」と捉え、戦略的にデザインする視点が不可欠です。
そして、その「出口」とは、若手の転職だけを指すものではありません。長年にわたり会社に貢献し、定年などを機に充実したセカンドキャリアへと巣立っていく大先輩の輝く背中もまた、会社がデザインすべき理想の出口の姿です。
短期のパートナーシップも、長期のパートナーシップも、その終わりを敬意と感謝で見送ること。その一貫した姿勢こそが、人生100年時代における企業の誠実さの証しとなります。 出口戦略を立て、それが機能し始め会社の文化に至るまでには相応の時間がかかりますので、早期の取り組みが期待されます。
著者 : 八丁宏志 (はっちょうこうじ)

クミタテル株式会社 取締役
1979年生まれ。専門学校卒業後、システム開発会社を経てIICパートナーズ入社。社内インフラの整備・運用からソフトウェアの開発・保守を手掛け、退職金・企業年金のコンサルティングにも従事。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに取締役に就任。人数規模、業種業態を問わず退職金制度を中心としたコンサルティングサービスを提供。