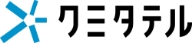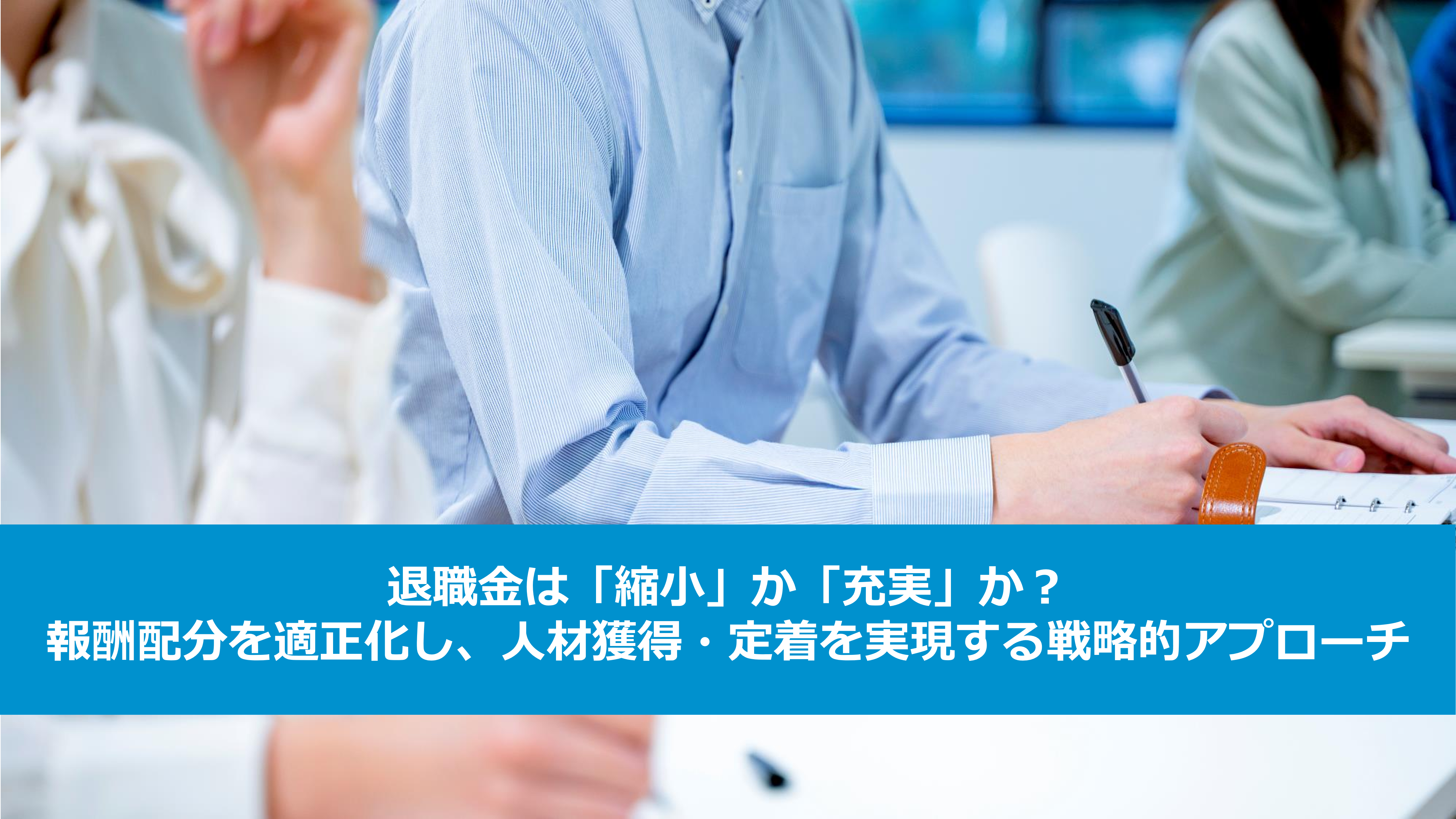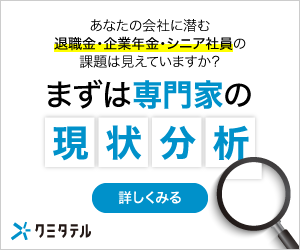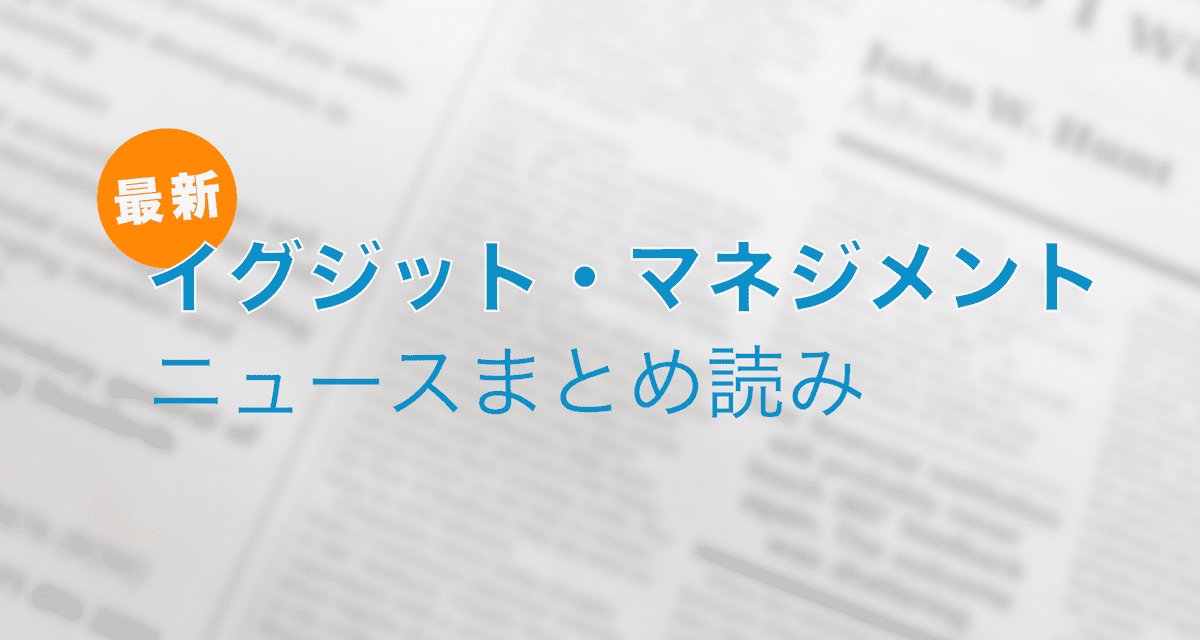高齢者雇用とシニア活躍推進に関するQ&A
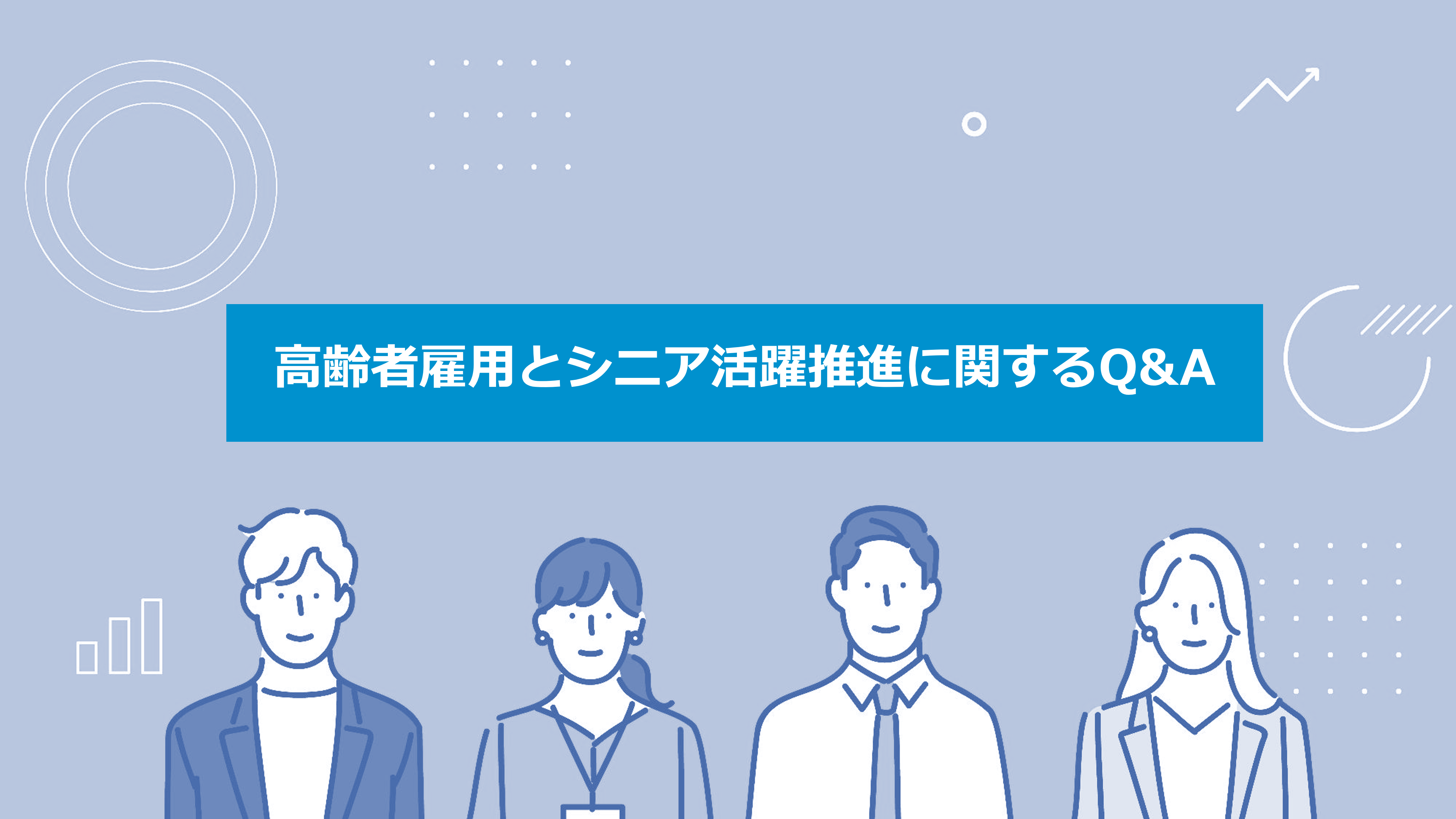
日本社会は急速な高齢化と労働力人口の減少に直面しており、企業にとって高齢者雇用とシニアの活躍推進は、もはや単なる選択肢ではなく、事業の持続性を確保するための不可欠な経営戦略となっています。
この記事では、経験豊富なシニア人材を最大限に活用し、組織全体の持続的な成長を実現するための考え方や制度設計について、Q&A形式で解説します。
Q1: なぜ今、高齢者雇用やシニアの活躍推進が企業にとって重要視されているのですか?
背景となる法改正と社会情勢
高齢者雇用が企業にとって喫緊の課題となっている背景には、法改正と社会情勢の変化が深く関わっています。2025年4月からは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が完全に施行され、企業は希望するすべての従業員を65歳まで雇用することが義務付けられます。この法改正は、単なる法的義務の履行に留まらず、企業の人材戦略に根本的な転換を迫るものです。
同時に、日本の生産年齢人口は少子高齢化の進行により減少し続けており、企業は優秀な人材の確保にますます苦慮しています。特に中小企業においては、労働力不足が深刻化しており、65歳以上の定年延長に積極的に取り組む動きも見られます。このような状況下で、長年にわたり培われた豊富な経験と知識を持つシニア層は、企業にとって代替不可能な貴重な戦力としてその価値を増しています。
経営戦略としてのシニア活用への転換
従来の高齢者雇用は、しばしば「福祉的雇用」の側面が強く、法的な雇用確保が主な目的とされてきました。しかし、現在の企業に求められているのは、シニア層を単なる「雇用維持の対象」として捉えるのではなく、「戦略的な戦力」として最大限に活用し、事業の継続と成長に貢献してもらうという根本的な姿勢の転換です。
この変化は、法改正が単なるきっかけに過ぎず、その根底には企業の経営戦略そのものが存在することを示唆しています。法的な義務を果たすことは最低限の要件であり、真に企業がシニア人材の活用に注力する動機は、人口減少に伴う人材不足の深刻化と、それに起因する競争激化への対応にあります。単に法律を遵守するだけに留まる企業は、戦略的にシニア人材を活用する企業に比べて、人材確保や組織の知識継承において後れを取る可能性が高いと言えるでしょう。
シニア社員が持つ長年の経験、専門知識、そして広範な人脈は、組織の多様な課題解決や、若手社員の育成、さらには新たな事業機会の創出に不可欠な要素です。彼らの活躍は組織全体の活性化に繋がり、企業の歴史や文化、暗黙知といった無形資産の継承にも大きく寄与します。
Q2: シニア社員の活躍を阻む主な課題や、従来の雇用制度の問題点は何ですか?
シニア社員の役割定義と主体性の課題
シニア社員の活躍を阻む主要な課題の一つは、企業側が彼らにどのような役割を割り当てるべきか、明確な定義ができていない点にあります。これにより、シニア社員自身も自身の貢献領域や、組織における存在意義を見出しにくくなる傾向があります。
また、企業はシニア社員に、自身の役割やキャリアパスを主体的に考えてほしいと期待するものの、現実にはそれがなかなか実現しないという課題も抱えています。これは、個人の意欲の問題として捉えられがちですが、実際には、定年に至るまで主体的にキャリアを選択する機会を設けてこなかった企業側の対応にも原因があります。
従来の「Will-Can-Must」フレームワークの限界
キャリア形成において広く用いられる「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(すべきこと)」のフレームワークは、個人の意欲と能力を組織のニーズに合致させる上で有効です。しかし、定年60歳を前提とした人事制度においては、シニア社員に対する「Must」が不在でした。
「Must」が明確に設定されていない状況では、高齢者雇用は「福祉的雇用」の域を出ず、単に法的な雇用義務を果たすことが目的となってしまいます。このような環境では、シニア社員が自身の仕事に意義を見出しにくくなり、モチベーションの向上や、能力を最大限に発揮できるような活躍機会の創出が極めて困難になります。シニア社員の主体性が不足していると見られる現象は、個人の資質の問題ではなく、組織が提供する役割や期待が不明確であるという制度設計の結果として現れているとも言えるでしょう。組織が明確な目的や役割を示さない限り、個人が自発的に自身の「Must」を創出することは困難であり、この課題の解決には人事制度や役割定義の抜本的な見直しが不可欠です。
報酬制度における課題
シニア社員の活躍を阻むもう一つの大きな要因は、報酬制度に関する課題です。多くの企業で、60歳以降の継続雇用において賃金水準が大幅に低下することが、シニア社員のモチベーション低下の大きな要因となっています。
賃金センサスのデータ分析によれば、大企業では特に60歳以降の賃金水準の低下幅が大きい傾向が見られます。さらに、業種によっても60歳以降の賃金落差が大きく異なることも示されており、一律の解決策を適用することが難しい現状が浮き彫りになっています。
この賃金水準の低下は、従業員が60歳に達することで一律に異なる賃金体系が適用されていることを意味しています。それは企業が60歳以降のシニア社員に対して、どのような役割や価値を期待し、それに対してどのような報酬を支払うべきかという「役割の価値」の再定義が遅れていることを反映していると考えることができます。このことは、報酬制度の課題が、シニア社員の役割定義の課題と密接に結びついていることを示唆しています。
Q3: シニア社員の能力を最大限に引き出すための新しいアプローチ「Will-Can-Offer」とは何ですか?
「Will-Can-Must」の限界と「Offer」の必要性
前述の通り、従来の「Will-Can-Must」フレームワークは、シニア社員に明確な「Must」が設定されていないため、彼らのモチベーションを引き出し、活躍を促す上で限界がありました。この課題を克服し、シニア社員の多様な経験やライフプランを考慮した上で能力を最大限に引き出すためにクミタテルが提唱しているのが、新しいアプローチである「Will-Can-Offer」です。
このアプローチでは、「Must」の代わりに企業側から「Offer(機会)」を提示します。シニア社員がこれまでに培ってきた「Will(やりたいこと)」と「Can(できること)」に対して、企業が具体的な「Offer」を示すことで、両者の合致点を見出し、新たな貢献の機会を創出することを目指します。
「Offer」の具体的内容とメリット
「Offer」とは、経営や事業計画の視点から、シニア社員に担ってほしい役割や職務内容を、それに対応する労働条件(賃金、勤務形態など)と共に具体的に提示するものです。これは単なる役割の提示に留まらず、企業と社員の間の対話を促す重要なツールとなります。
第一に、企業は「Offer」を通じて、人材不足が深刻化する中でシニア社員を戦略的に活用し、事業の継続と成長を図ることができます。これは、単に雇用を維持するだけでなく、彼らを積極的に事業に組み込むことを意味します。
第二に、企業が事前に「Offer」を提示することで、社員は自身のキャリアの後半に向けて準備を進めることができます。例えば、必要なスキルを習得したり、新たな役割への心構えをしたりする時間的猶予が生まれます。また、社内に自身の「Will」や「Can」に合致する適切な「Offer」がない場合でも、社員は社外の機会を検討するという選択肢を明確に持つことができます。これは、従業員が自身のキャリアを自律的に設計する上での透明性と選択肢を提供します。
ジョブ型雇用との関連性
「Will-Can-Offer」の考え方は、職務に対して等級や報酬を設定する「ジョブ型雇用」と高い親和性を持っています。ジョブ型雇用は、個人の能力や経験だけでなく、実際に担う職務の価値に基づいて報酬を決定する仕組みであり、シニア社員の役割と貢献を明確に評価する上で非常に有効です。このアプローチは、シニア社員だけでなく、全社員に適用可能な人事制度改革の方向性を示唆しています。
しかし、従来の年功序列型やメンバーシップ型雇用が根強い日本企業において、全社員へのジョブ型雇用の一斉導入は難易度が高いのが現状です。そのため、まずはシニア社員に対する「福祉的雇用」から「戦力化」への転換の第一歩として、この「Will-Can-Offer」フレームワークを導入することが、現実的かつ効果的なアプローチとして考えられます。
シニア層へのこのアプローチの導入は、全社的な人事制度改革の試金石となる可能性があります。シニア社員の活用における課題(役割定義、期待値管理、貢献に応じた報酬設定など)は、企業が人材活用をより戦略的に考えることを促します。この層での成功事例は、より広範な従業員層へのジョブ型雇用への道を開き、組織全体の変革を加速させる可能性を秘めていると言えるでしょう。
Q4: シニア社員の賃金動向はどうなっていますか?
若手並みの上昇率を示すシニアの賃金
厚生労働省が毎年実施する「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)のデータ分析によると、2020年から2024年の期間において、60代前半の平均賃金は初任給を含む若年層の賃金上昇率に匹敵する伸びを示しています。これは、企業がシニア社員の処遇改善に積極的に取り組んでおり、彼らを単なる雇用維持の対象ではなく、より戦略的な戦力として評価し始めていることを強く示唆しています。
特に注目すべきは、60代前半の非正規社員の賃金動向です。この層の賃金は、2020年比で12%を超える大幅な上昇を見せています。この事実は、定年延長制度を導入していない企業であっても、継続雇用制度の見直しを通じて高齢社員の処遇改善が進んでいることを示しています。シニア賃金の上昇は、労働市場における「経験価値」の再評価と「需要と供給」の原則の明確な表れです。若年労働人口の減少により、経験豊富なシニア人材への需要が高まり、企業は彼らを確保・活用するために、それに見合った報酬水準へと見直しを進めています。
企業規模・業種による賃金格差の特性
賃金センサスのデータからは、企業規模や業種によってシニア社員の賃金動向に顕著な差異があることも見て取れます。
企業規模による差異:
賃金水準は、20代前半では企業規模による差が小さいものの、50代にかけて大企業ほど高くなる傾向があります。しかし、60歳以降は企業規模による差が再び縮小し、結果的に大企業の方が賃金水準の低下幅が大きい傾向が見られます。中小企業のほうが65歳以上の定年延長などシニア社員の戦力化に積極的なのは、労働力不足であることに加えて、現役世代との賃金格差がもともと小さいことも背景にあるものと考えられます。
業種による顕著な差:
60歳前後の賃金格差は業種によっても大きく異なります。例えば、「電気・ガス・熱供給・水道業」や「情報通信業」では、50代後半の賃金水準が非常に高いものの、60代前半で大幅に低下する傾向があります。対照的に、「教育、学習支援業」では60歳前後の賃金差がほとんどなく、60代前半の賃金水準が全業種で最も高い水準にあります。これは、各業種の事業特性や雇用慣行が、高齢者雇用の「雇用確保から戦力活用への転換」の進捗度合いに影響を与えているためと考えられます。
詳細は下記の解説記事にまとめていますのでご覧ください。
Q5: 定年延長や再雇用制度において、シニア社員の報酬制度をどのように設計すべきですか?
報酬制度設計の基本原則
シニア社員の報酬制度を設計する上で最も重要な原則は、単に年齢や勤続年数に基づくのではなく、彼らが担う「役割の価値」と、組織への「実際の貢献度」に基づいて設計されるべきであるという点です。この考え方は、職務の価値に応じて報酬を定めるジョブ型雇用の思想とも合致します。
報酬水準の維持も重要ですが、それ以上に、シニア社員が自身の仕事に価値を見出し、モチベーションを維持できるような仕組みを構築することが不可欠です。そのためには、報酬の決定プロセスにおける透明性を確保し、評価基準を明確にすることで、社員の納得感を高めることが極めて重要となります。
賃金水準の低下がシニア社員の意欲を削ぐ要因となることは明らかですが、重要なのは単なる金額の多寡だけでなく、その報酬が明確な役割と貢献に見合っていると社員が納得できるかどうかにあります。ジョブ型のように仕事の価値に報酬を紐づけ、その条件を事前に明確に提示することで、企業は透明性と公平性を確保し、社員のモチベーションを維持することができます。これは、単なる「減額」ではなく、新たな条件に基づく「契約」への移行として捉えられ、シニア社員の貢献意欲を維持する上で不可欠な要素となります。
報酬制度設計における考慮点
シニア社員の報酬制度を設計する際には、働き方の柔軟性を考慮することも重要となります。フルタイムでの継続雇用だけでなく、短時間勤務、専門職としての契約、プロジェクト単位での参画など、多様な働き方とそれに対応する報酬体系を検討することが、シニア社員の選択肢を広げ、活躍を促します。また、働き方を柔軟に選択できる制度設計は、シニア社員が自身のキャリアプランやライフプランを明確化することにもつながり、彼らの自律的なキャリア形成を支援します。
シニア層へのこうした報酬制度の導入は、全社的に多様な働き方を推進するための第一歩にもなります。ワークとライフの両立はシニア世代だけでなく全世代にとっての大きな関心事であり、多様な働き方への対応は労働力不足への対応を考える上で重要なピースとなります。
Q6: 高齢者雇用・シニア活躍推進は「イグジットマネジメント」においてどう位置付けられますか?
イグジットマネジメントの定義と重要性
イグジットマネジメントとは、従業員の退職やキャリアの「出口」を単なる離職として捉えるのではなく、組織全体の活性化や持続的な成長に繋がる戦略的なプロセスとして管理する考え方です。高齢者雇用やシニアの活躍推進は、このイグジットマネジメントの重要な一環として位置づけられます 。
適切なイグジットマネジメントは、組織内の人材の流動性を適度に維持し、新陳代謝を促進します。これにより、新たな才能の流入や、既存社員のキャリアパスの多様化が可能になり、組織が常に変化に対応できる状態を保つことができます。
高齢者雇用とイグジットマネジメントの関係
高齢者雇用はイグジットマネジメントにおいて多岐にわたる重要な役割を担います。
第一に、シニア社員に対して、定年後の継続雇用だけでなく、セカンドキャリア支援、独立支援、あるいは社外での活躍を促すための情報提供やスキルアップ支援など、自身のライフプランに合わせた多様な「出口」を選択できるような支援を提供します。これは、社員が自律的に自身のキャリアをコントロールすることを促します。
第二に、シニア社員が退職する際、彼らが長年培ってきた貴重な知識や経験が組織から失われないよう、計画的な引き継ぎやナレッジマネジメントの仕組みを組み込むことが重要です。これにより、組織の知的資産が次世代へと円滑に継承されます。
第三に、シニア社員の退職や新たな役割への移行を戦略的に管理することで、組織内のポストが流動化し、若手・中堅社員への成長機会創出に繋がります。これは、組織全体のモチベーション向上と活性化に貢献します。
イグジットマネジメントは、単なる「退職管理」ではなく、「戦略的な人材パイプライン管理」の最終段階と位置づけられます。従来の退職管理が往々にして事務的な手続きに終始するのに対し、イグジットマネジメントは、従業員が組織を「どのように去るか」(あるいは組織内でどのように移行するか)が、将来の人材プール、知識基盤、そして企業文化に大きな影響を与えるという認識に基づいています。
戦略的に「出口」を管理することで、企業は人材の継続的な流れを確保し、重要な知識の喪失を防ぎ、他の従業員に成長の機会を提供することができます。これは、組織が常に適切な人材を適切な役割に配置できるよう、入社から退社までの一連の「人材パイプライン」全体を最適化する取り組みと言えるでしょう。
「人材を『定着』させるな」という逆転の発想は、従来のHRパラダイムに挑戦するものです。これは、社員を積極的に追い出すという意味ではなく、社員が新たな役割で社内に留まるか、社外で機会を追求するかといった自律的なキャリア決定を支援する環境を育むことを意味します。企業が画一的な「定着」に固執せず、常に役割を再評価し、新たな「Offer」を創出し、変化する人材ニーズに適応することで、社員の「自律性」を高めると同時に、企業自身の「適応力」も向上させます。これにより、組織は停滞することなく、より機敏で活力ある状態を保つことができるのです。
まとめ:戦略的なシニア人材活用に向けて
・高齢者雇用は、高年齢者雇用安定法の完全施行を契機に、単なる法令遵守を超え、人材不足時代における企業の「戦略的戦力化」が不可欠となっています。
・従来の「福祉的雇用」が抱える役割不明確やモチベーション低下といった課題を克服するためには、「Will-Can-Offer」のような新しいアプローチが有効です。これにより、シニア社員の主体性と組織への貢献意欲を最大限に引き出すことが可能になります。
・賃金センサスのデータは、60代前半のシニア社員の賃金が若年層並みに上昇していることを示しており、これは労働市場におけるシニアの経験価値が再評価され、企業が彼らを戦略的な戦力として捉え始めていることを示唆しています。報酬制度は、役割と貢献に基づいた透明性のある設計が求められます。
・イグジットマネジメントは、シニア人材の活用を含む、組織全体の人材パイプラインを最適化し、新陳代謝を促進するために不可欠な戦略的プロセスです。
これらの知見を踏まえ、企業が今後取り組むべき方向性は以下の通りです。
・人事戦略の再構築: シニア人材を単なる「コスト」ではなく「投資」と捉え、全社的な人材戦略の中に明確に位置づける必要があります。これは、長期的な視点での人材育成と活用計画を意味します。
・多様な働き方とキャリアパスの提供: シニア社員の多様なニーズに応えるため、フルタイム継続雇用だけでなく、短時間勤務、専門職契約、プロジェクト参画など、柔軟な勤務形態や社内外のキャリアパスを提示することが重要です。
・継続的な対話と支援: 全世代に対して継続的にスキルアップやリスキリングの機会を提供することで、彼らが自律的にキャリアを形成し、年齢にかかわらず変化に対応できるよう支援を続けるべきです。
シニア人材の戦略的な活用は、企業の持続可能性を高めるだけでなく、多様性を尊重し、すべての世代がそれぞれの経験と能力を活かして活躍できる「共創」の組織文化を醸成することに繋がります。これは、単に高齢者問題を解決するだけでなく、企業全体の競争力を高め、より豊かな社会を築くための重要な一歩となるでしょう。
クミタテル編集部

クミタテル編集部が退職金や確定拠出年金などの情報をご紹介していきます。