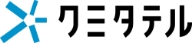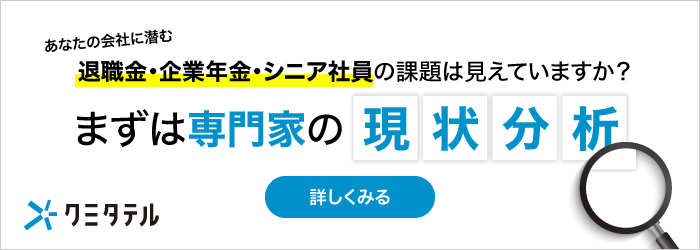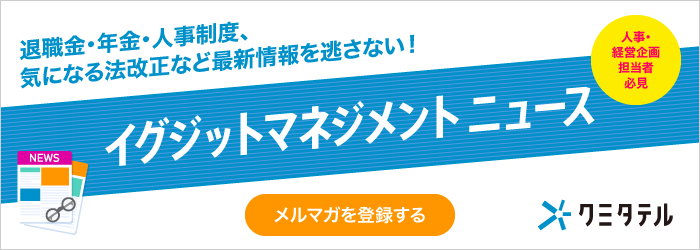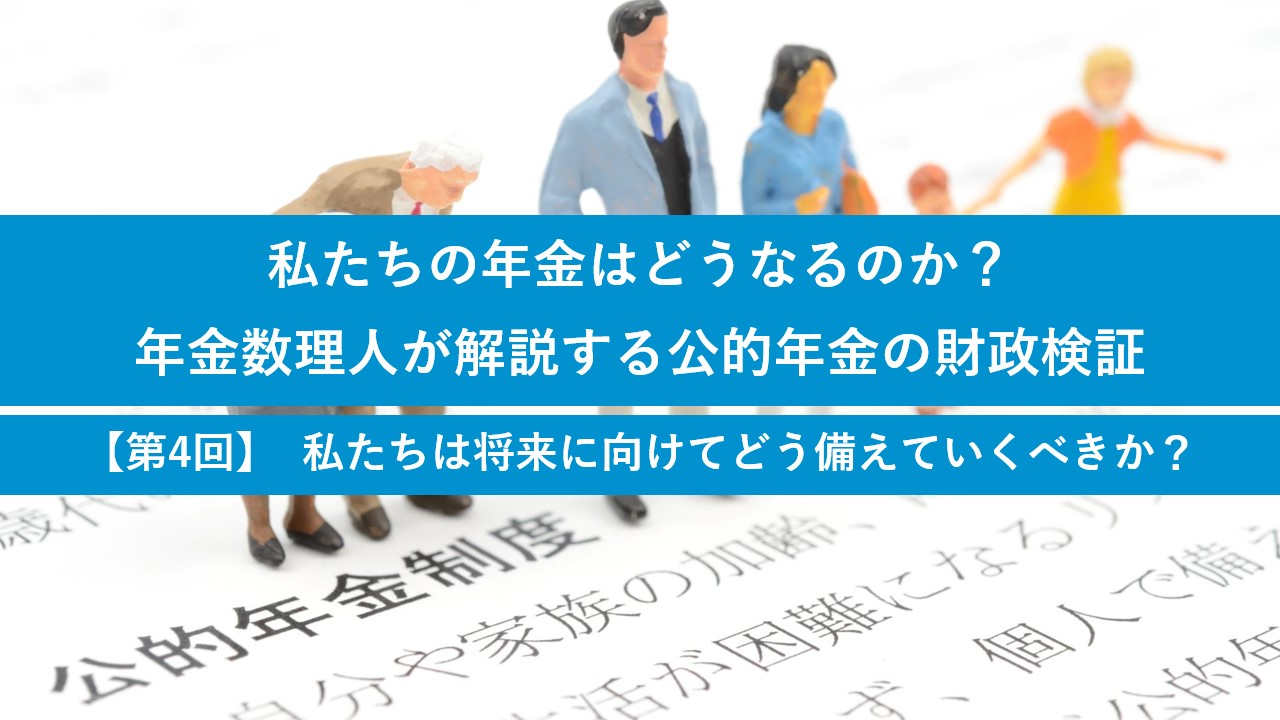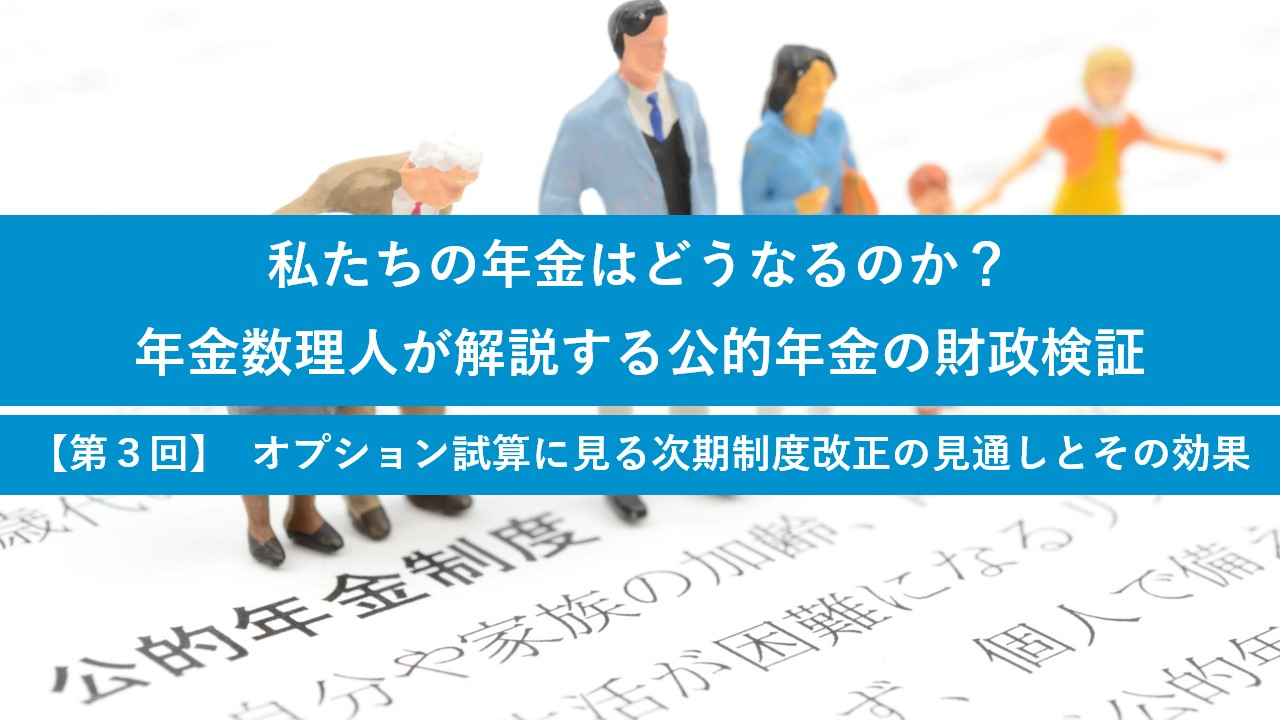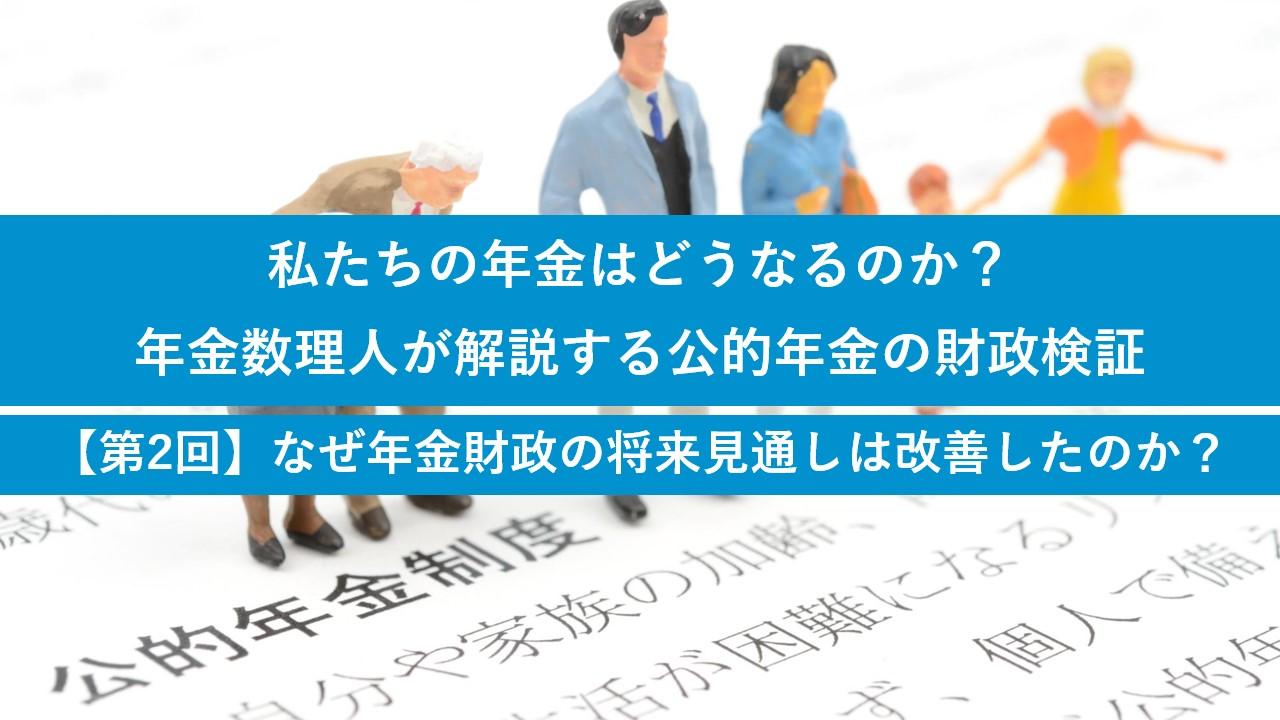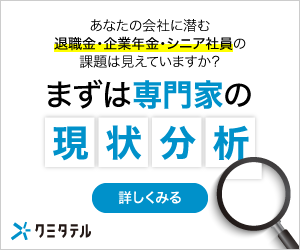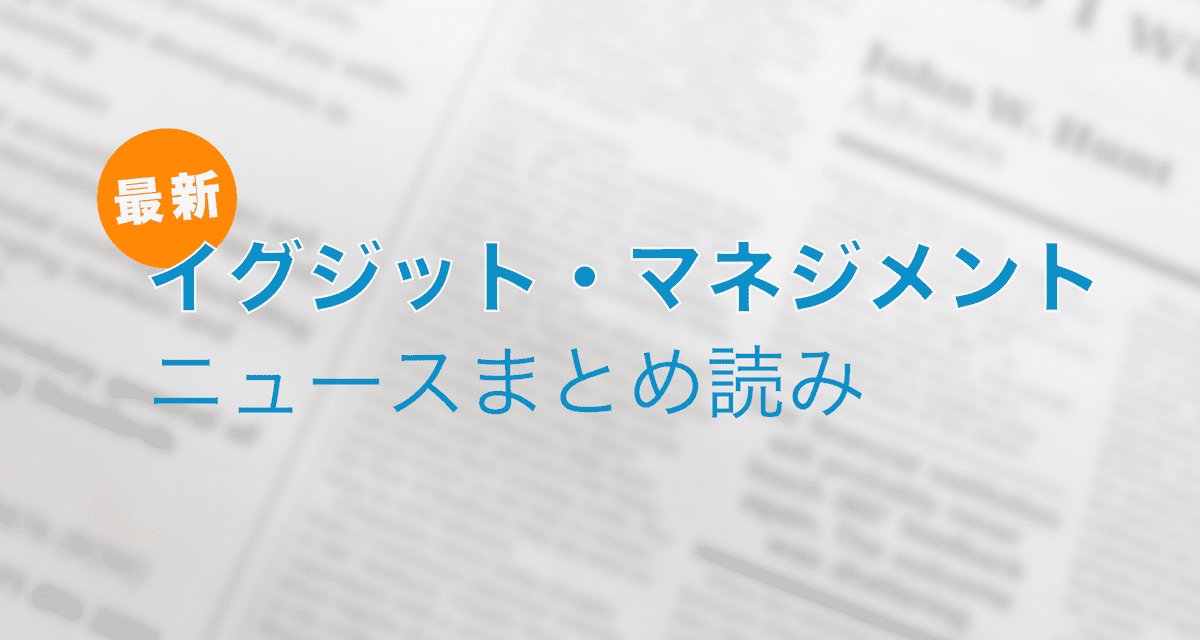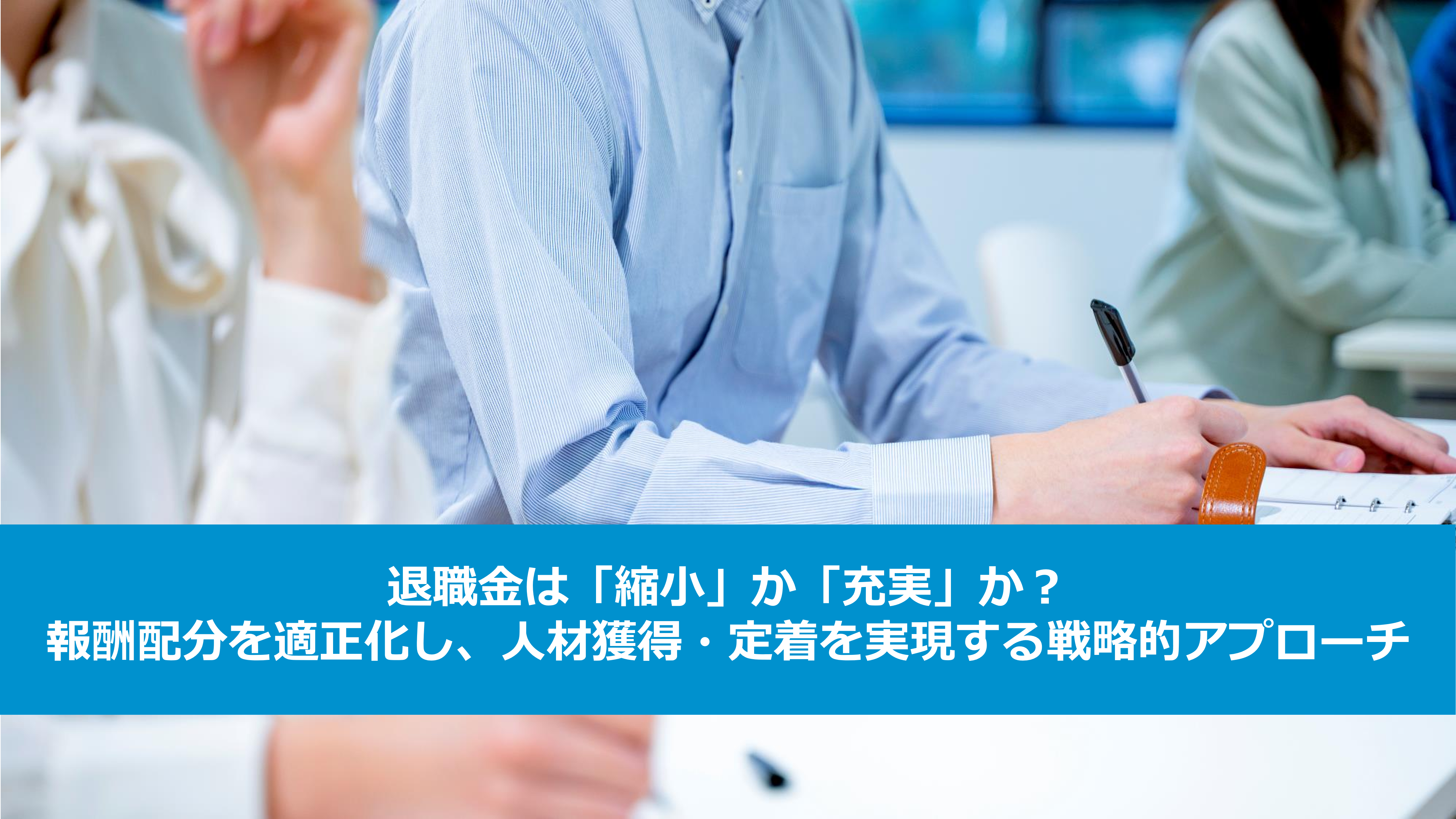【人事必見】第1回 シニア人材の効果的な活用とは? | 連載「70歳就労時代のシニア人材向け研修の重要性とは?」
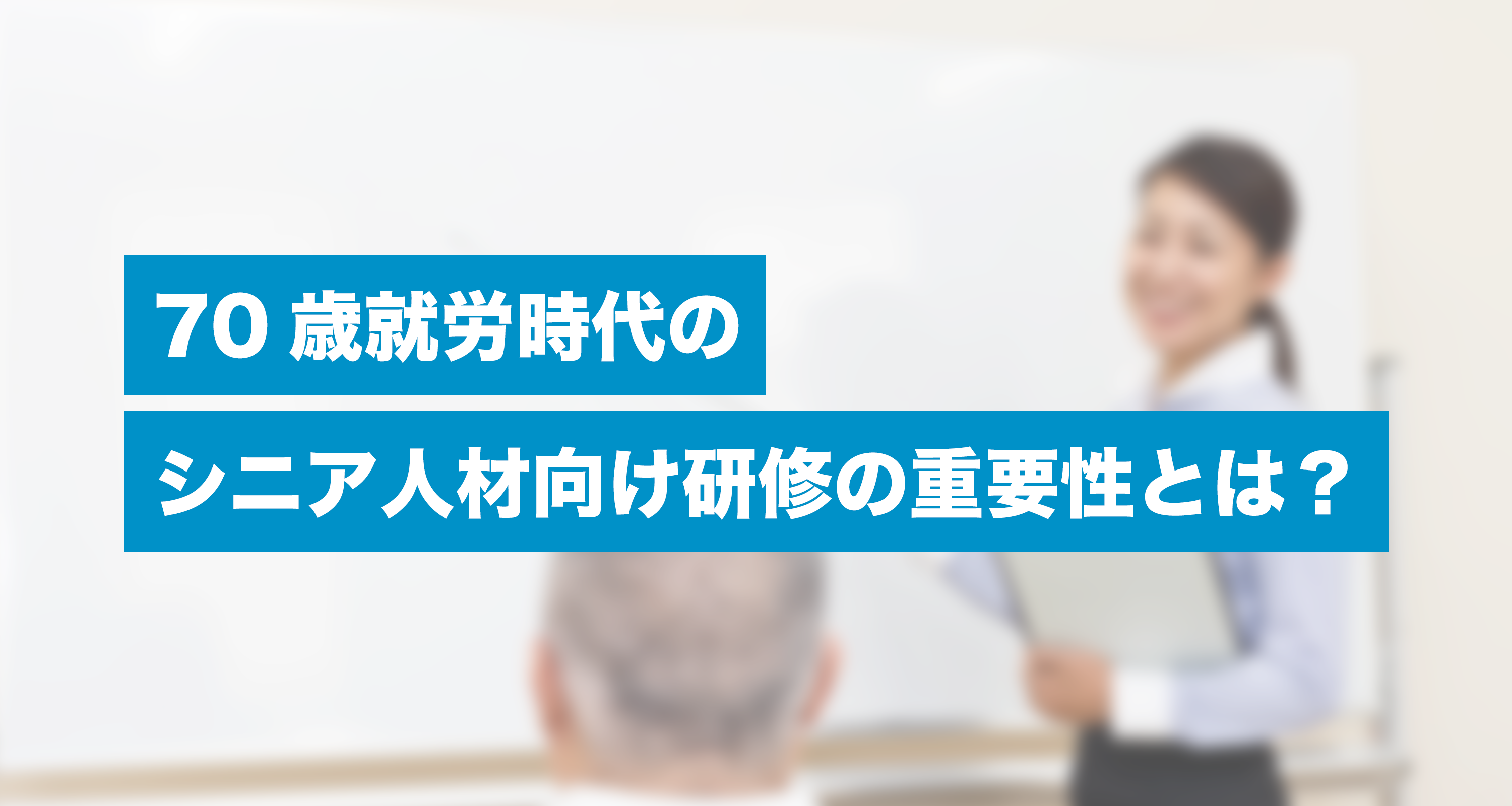
2021年4月より高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業機会を確保する施策が実行されることとなりました。
これに伴って、シニア人材の活用や役割の設定方法などについて弊社にも多くの問い合わせをいただいており、今まで以上にシニア人材に注目が集まっていると感じます。また、私自身、前職では尊敬できる上長や同僚が60歳を超しており、優秀なシニア層と共に仕事に取り組めたことが20代の成長に大きく影響したと確信しています。
本記事では約3回に分け、シニア人材向けの研修を中心にシニア人材の活用方法や与えるべき役割、研修企画のポイントなどを紹介していきます。
企業の抱えるシニア人材の課題
まず、シニア人材に注目が集まっている背景となるシニア人材の課題について見てみましょう。 弊社がお客様からよく相談を受ける課題を列挙しますので、自社のシニア人材における課題について考えてみましょう。
【多くの企業が抱えるシニア人材における課題】
✔︎ 報酬や処遇の適正化
✔︎ モチベーションの低下
✔︎ シニア人材に適した業務の手当・拡充 (役割)
✔︎ パフォーマンスの低下
✔︎ 健康上の配慮 他
多くの方が、少なくとも一つは自社にも当てはまると感じたのではないでしょうか。 実際に弊社がよくお問合せを受けている内容でもあり、主催するセミナー後のアンケート調査でもよく挙げられる課題項目となっています。
シニア人材が活躍するためのポイント
ここからは、シニア人材における課題を解決するために必要となるポイントを3つご紹介します。 まず、一つ目としては、報酬や処遇の適正化です。日本人の8割近くが老後のお金に不安を抱いていると言われる通り、報酬の多寡や頑張っても評価がされにくいようでは、モチベーションは下がる一方かと思います。
また、60歳以降は一律給与が引き下がる、もしくは、本人の能力や仕事内容に関係なく給与が引き下がる、といった実質的にシニア層の働きに期待をしていないと暗にメッセージを打ち出してしまっているケースも散見されます。これらは、高齢者雇用に関して福祉的要素が非常に強く、シニア層の社員が増加した場合にうまく回らなくなるケースが多いように思います。
これらを防ぐために、次で説明をするポイントとの連携が重要になってきます。
二つ目として役割の明確化です。この役割とは、どのような職責で会社がシニア社員に何を求めているかを明確化することです。言い方を変えますと、会社は従業員から何を買って、従業員は会社へ何を提供するのかを明確化することです。
一つ目の給与と合わせて、会社は、シニア社員になぜその仕事をしてもらい、どうしてその報酬になるのかを明確化していくことがシニア社員への納得感に繋がるため重要になってきます。最近の流れとしては、一律で仕事内容や役割を与えるのではなく、いくつかのコースを設け、マネジメントを継続する高パフォーマンスの方向けのコース、後進の育成やマネジメント以外のプロフェッショナル業務を行う方向けのコース、比較的単純化された業務で就労時間も柔軟に働くことができる方向けのコースなど設計していくことも挙げられます。
最後にシニア人材自身の人生を考える場の提供です。これは、シニア人材向け研修を指しており、前述の2つのポイントである処遇や役割の変化に対し、従業員自身が納得感を持ってもらうための役割を果たします。
よく見る失敗例として、処遇や役割などをしっかりと作り込めているが、従業員への説明のタイミングが定年直前で従業員の気持ちが制度に追いついていかないということが挙げられます。最近の流れとしては、50歳前後に自社の制度に関して説明を行い、従業員自身の老後の生活も意識しながら、会社との繋がりを考えていく、「心の準備期間」を儲けるためのきっかけ作りの研修も採用され始めているように思います。
特に右肩上がりで成長してきた人生から停滞または下がることを受け入れるのは簡単ではありませんので、そのための準備期間も重要な要素になってきます。
生き生きとしたシニア人材になってもらうために必要なこと
生き生きとしたシニア人材になってもらうためには、前述の3つのポイントである処遇・役割・研修をうまく連動しながら運営していくことが大事なのでは無いでしょうか。
処遇や役割をしっかり作っていても、それを正しく伝えることができなければ、思うような効果が出ない可能性が高まります。シニア社員自身も今までのキャリアの延長線上にはない選択をする必要が出てきますので、正しく会社の狙った効果が現れるように仕組みを伝える研修にも力をさく必要が出てきていると感じます。
次回では、設定した処遇や役割の効果を最大化するシニア向け研修の紹介をしていきます。
「第2回 制度を効果的に活用させるシニア社員向け研修のポイント」を読む >
金融教育を相談したいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
著者 : 石川 泰 (いしかわ たい)

1991年生まれ。東京理科大学基礎工学部卒業後、2015年に株式会社IICパートナーズへアクチュアリー候補として入社。その後、野村證券株式会社にて確定拠出年金に関する法人営業、SBIベネフィット・システムズ株式会社において、関係省庁や業界団体との折衝、企画業務を担当。
現在はクミタテル株式会社で働く他、2021年1月に設立した公的私的年金・退職金の一元管理を目指したフィンテック企業の代表も務める。
SBI大学院大学経営管理研究科(MBA)卒業、元プロボクサー(1戦1勝1KO)。
出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう
労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。
シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。