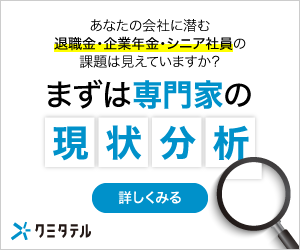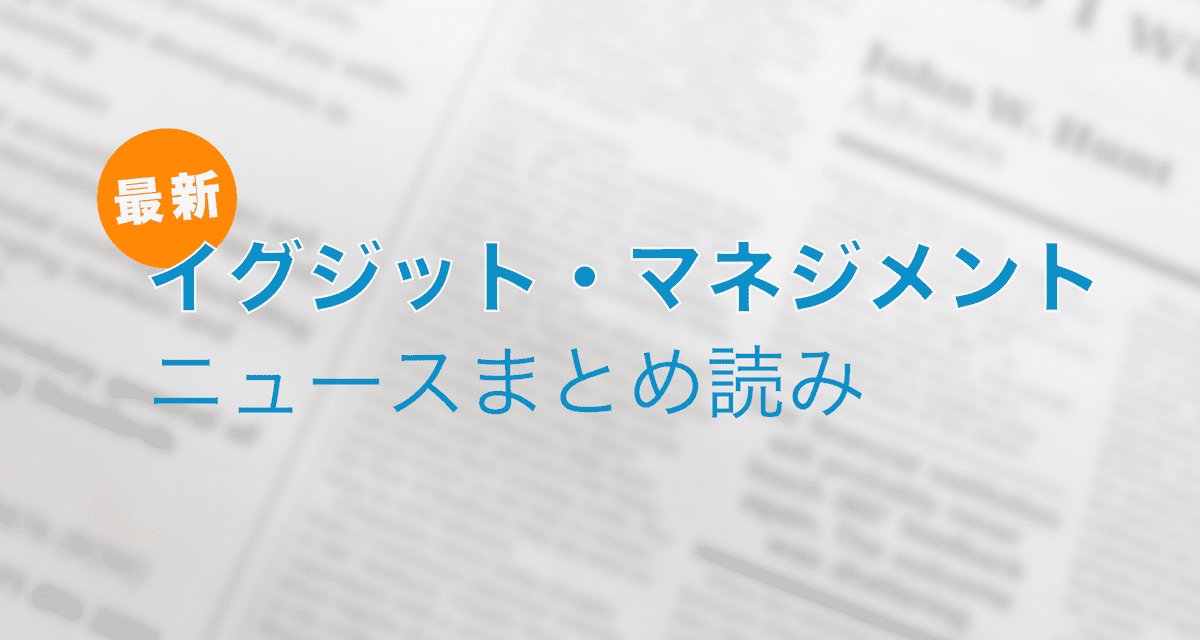人事担当者なら知っておきたい、高齢者雇用と退職金・企業年金の税制
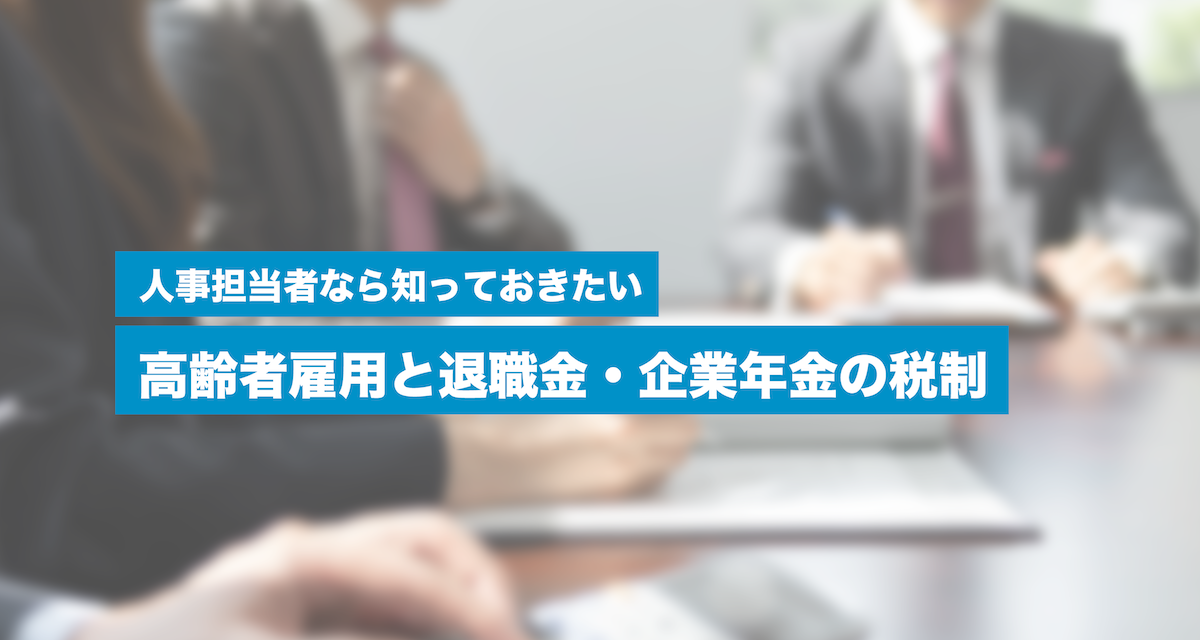
定年延長など高齢者雇用制度の見直しは退職金・企業年金にも影響を及ぼすため、退職給付制度の見直しもセットで考える必要があります。このとき、考慮に入れておかないといけないのが税制です。企業人事としては、税制上の取り扱いによって従業員が不利益を被ることがないよう注意しておかなければなりません。
今回は、退職金・企業年金に関する基本的な税制を整理したうえで、定年延長や再雇用制度の見直しに関連する税制上の留意点について解説します(2022年現在の税制に基づく)。なお、個別の取り扱いについては所轄の税務署や税理士にご確認ください。
退職金・企業年金にかかる税金の基本的な考え方
退職後に受け取る退職金・企業年金にかかる税金(所得税)の扱いは、一時金(一括支給)か年金(分割支給)かで以下のように大きく2つに分かれます。
| 一時金 | 年金 | |
| 所得の区分 | 退職所得 | 雑所得 |
| 課税方式 | 分離課税(退職所得のみで別に税額を計算) | 総合課税(他の所得と合計して税額を計算) |
| 控除等の適用 | 退職所得控除(下記①参照)を適用し、さらに1/2する | 公的年金等控除(下記②参照)を適用する |
① 退職所得控除
勤続年数が20年以下の場合、40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数が20年超の場合、800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数の1年未満の端数は切り上げ
② 公的年金等控除
| 受給者の年齢 | 受け取る年金額 | 控除額 |
| 65歳未満 | 60万円以下 | 年金額の全額 |
| 60万円超130万円以下 | 60万円 | |
| 130万円超410万円以下 | 年金額×25%+27.5万円 | |
| 410万円超770万円以下 | 年金額×15%+68.5万円 | |
| 770万円超1,000万円以下 | 年金額×5%+145.5万円 | |
| 1,000万円超 | 195.5万円 | |
| 65歳以上 | 110万円以下 | 年金額の全額 |
| 110万円超330万円以下 | 110万円 | |
| 330万円超410万円以下 | 年金額×25%+27.5万円 | |
| 410万円超770万円以下 | 年金額×15%+68.5万円 | |
| 770万円超1,000万円以下 | 年金額×5%+145.5万円 | |
| 1,000万円超 | 195.5万円 |
※年金以外の所得が年間1,000万円超2,000万円以下の場合は一律10万円、年金以外の所得が年間2,000万円超の場合は一律20万円、上記の金額よりも控除額が小さくなる。
【計算例①】勤続30年の人が1,600万円の退職一時金を受け取った場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
課税対象となる退職所得の額=(1,600万円-1,500万円)×1/2=50万円
【計算例②】60歳の人(年金以外の所得は年間1,000万円未満)が1年間で200万円の年金を受け取った場合
公的年金等控除の額=200万円×25%+27.5万円=77.5万円
課税対象となる雑所得の額=122.5万円
上記のとおり、特に退職所得については大きな控除が設けられており、一時金で受け取る退職金は税制上優遇されています。
定年延長が退職一時金の税金に与える影響と留意点
定年年齢を60歳としている企業では、再雇用の有無にかかわらず60歳の定年到達時に退職金を支給しているのが一般的です。実際にはその後再雇用により継続して雇用される場合であっても、定年到達時に退職金として支給される一時金は退職所得に該当します(再雇用の終了時などその後に支給される退職金が別にある場合は、定年前の勤続期間を一切加味しないことが前提)。
一方で定年年齢を引き上げた場合は(例として65歳に引き上げた場合を考える)、引き続き勤務する社員は65歳で初めて「退職」を迎えることとなるため、退職金の支給時期は65歳の定年到達時とするのが原則的な扱いとなります。
そのため、支給時期が5年間先送りになる代わりに、退職金を受け取るまでの勤続年数は5年間延長され、一時金で受け取る場合の退職所得控除額が増えることになります。上記の計算例①に当てはめると、退職金の額は1,600万円で変わらなかったとしても、退職所得控除額は1,850万円(=800万円+70万円×(35年-20年))となって退職金の額を上回るため、結果として全額非課税となり手取りの金額は増えることになります。なお、定年延長後の退職金の額に60歳以降の勤務期間を反映させない(退職金の額を定年延長前と同額とする)場合であっても、実際の勤務期間を勤続年数として退職所得控除額を計算します。
このように、定年延長時には基本的に退職金の支給時期も同様に延長されることとなりますが、もともと60歳到達時に支給されるはずだった退職金が65歳になるまで支給されなくなるのは社員にとって不利益となります。そのため、定年延長後も経過的に60歳(旧定年)到達時に従前どおり退職金相当額を支給する対応をとるケースもあります。
ただし、税制上退職所得に該当するのは原則として「退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」とされており、退職していないにもかかわらず支給される「退職金」は税制上給与所得となり、多額の税金がかかってしまいます。この点、引き続き勤務する人に支払われる給与で例外的に退職所得とするものの1つとして以下の項目が定められています。
※所得税基本通達30-2より抜粋(下線部は筆者による)
この中で「相当の理由」に該当するための基準などは明確に示されていませんが、国税庁が公表している文書回答事例では、以下のような条件のもとで旧定年で支給される退職金相当額を退職所得として認めています。
・ 定年延長前に入社した社員に対する措置であること
・ 定年を延長した期間に対する退職一時金の支給はなく、定年延長にかかわらず退職一時金の額に変更はないこと
・ 定年延長後も60歳以降の給与水準は60歳前と比較して大きく低下すること
・ 退職一時金の支給時期の延長が社員の生活設計に影響を及ぼすこと
ただし文書回答事例はあくまで個別の照会に対する回答事例であって、統一的な税制上の取り扱いを示したものではありません。定年延長後も引き続き旧定年で退職一時金を支給することとしたい場合には、事前に所轄の税務署に確認を取っておくのがよいでしょう。
再雇用後の勤務期間に対する退職一時金の税金
定年後再雇用により継続雇用を行う場合に、定年到達時に支給する退職一時金とは別に、再雇用期間に対する退職一時金を再雇用の終了時に支給するケースがあります。この再雇用終了時の退職一時金も退職所得に該当し、再雇用期間を勤続年数とみなして退職職控除額が計算されます。
例えば、再雇用期間が60歳から65歳までの5年間である場合の退職所得控除額は200万円(=40万円×5年)となり、再雇用終了時の退職一時金がこの範囲内であれば非課税となります。また、仮に200万円を超えた場合でも課税対象となる所得はその1/2となります。つまり、再雇用期間における報酬の一部を給与や賞与ではなく退職金として受け取ることで税制上は有利になるといえます。
ただし、勤続年数が5年以下である場合の退職一時金については「短期退職手当等」として、税制優遇措置に一定の制限が設けられています。具体的には、退職一時金額から退職所得控除額を差し引いた残額が300万円を超える部分については1/2課税が適用されません。
【計算例①】勤続5年で500万円の退職一時金を受け取った場合
退職一時金額から退職所得控除額を差し引いた残額=500万円-200万円=300万円
→残額のすべてが1/2課税の適用対象
課税対象となる退職所得の額=300万円×1/2=150万円
【計算例②】勤続5年で600万円の退職一時金を受け取った場合
退職一時金額から退職所得控除額を差し引いた残額=600万円-200万円=400万円
→残額のうち100万円は1/2課税の適用対象外
課税対象となる退職所得の額=300万円×1/2+100万円=250万円
確定給付企業年金(DB)からの給付にかかる税金
確定給付企業年金(以下「DB」)からの給付のうち年金(老齢給付金)については、「基本的な考え方」のところで説明したとおり公的年金等控除の対象となり、雑所得として課税されます。公的年金等控除額は、各年末時点の年齢と、その年に支給されるべき年金額(老齢厚生年金や老齢基礎年金など公的年金等控除の対象となる年金を合算した金額)によって決まります。そのため、定年延長などに伴って年金の支給時期が変わると課税対象となる雑所得の金額も変わることがありますが、退職の有無や勤続年数が直接影響することはありません。
一方で退職により支給される一時金(脱退一時金または選択一時金)については、退職一時金と同様に退職所得に該当します。このとき、退職所得控除額の計算に用いる勤続年数は支払金額の計算の基礎となった期間とされ、必ずしも実際の勤続年数とは一致しません。
例えば、定年年齢を60歳から65歳に延長したことに伴い、DBに加入する期間も65歳まで延長した場合は、その分退職所得控除額の計算に用いる勤続年数も延びます。しかし、定年延長後も60歳で資格喪失することとし、その後65歳まで支給を繰下げて一時金を受け取る場合は60歳までの期間により退職所得控除額が計算されます。会社から支給する退職一時金については、前述のとおり60歳以降の勤務期間を反映させない場合であっても実際の勤務期間を勤続年数として退職所得控除額を計算しますが、DBでは取り扱いが異なる点に注意が必要です。
また、定年延長後も60歳で資格喪失することとした場合、それ以降勤務を継続するにもかかわらず60歳時点で一時金を受け取ったときには一時所得になるのが原則的な考え方になります。一時所得については収入額から50万円を控除した残額の1/2が所得金額となるため(総合課税)、退職所得に比べて控除額が非常に小さく不利になります。そのため、実際の退職時期まで支給の繰下げを可能としておくか、旧定年での支給が例外的に退職所得として認められるかを事前に所轄の税務署に確認を取っておくのがよいでしょう。
旧定年での(退職金相当の)一時金支給が退職所得として認められる要件は「定年延長が退職一時金の税金に与える影響と留意点」のところで紹介したとおりですが、会社から支給する退職一時金がある場合、旧定年で支給されるDBからの一時金が退職所得として認められるためには、会社退職金も併せて旧定年時に支給されることが要件の1つとなっています(DBの一時金のみ旧定年時に支給する場合は一時所得となる)。
また、DBで支給を繰下げたときの一時金は、それがどの年の退職所得になるのかについても注意が必要です。例えば、60歳に退職、資格喪失し、支給を繰下げて65歳で一時金を受け取った場合、それまでに会社から退職一時金の支給がなければ、65歳時の年の退職所得となります。これに対して、60歳の退職時点で会社から退職一時金の支給があった場合には、65歳時に支給されるDBの一時金も退職一時金と同じ年の退職所得として扱われます。これは、「一つの退職に起因して複数の退職所得がある場合、このうち最初に支払われるものの属する年の収入とする」というルールがあるからです。したがって、「DBの繰下げによって退職一時金と支給の時期をずらすことで退職所得にかかる税金を減らす」ということはできません。
確定拠出年金(DC)からの給付にかかる税金
確定拠出年金(以下「DC」)に関しても、老齢給付金として支給される年金についてはDBと同様の扱いとなります(公的年金等控除の対象、雑所得として課税)。定年延長などに伴い年金の支給時期が変わることで課税対象となる雑所得の金額も変わることがありますが、退職の有無や勤続年数が直接影響することはありません。
一方で、老齢給付金として支給される一時金(以下「老齢一時金」)については、退職一時金やDBの一時金と同様に退職所得に該当します。このとき、退職所得控除額の計算に用いる勤続年数は、老齢一時金の基礎となるDCの加入者期間(掛金拠出期間)とされ、他の制度から移換された資産が含まれている場合には、その移換により通算された加入者期間も含まれます。したがって、必ずしも実際の勤続年数とは一致しません。
高齢者雇用との関係では、定年年齢を60歳から65歳に延長したとしても、企業型DCの資格喪失年齢が60歳のままであれば60歳以降の勤務期間は退職所得控除額の計算に反映されません。しかし、60歳から個人型DC(iDeCo)に加入して企業型DCの資産をiDeCoに移換した場合は企業型DCの加入者期間が通算され、iDeCoの一時金を受け取る際には60歳以降の加入者期間も加えて退職所得控除額を計算します。なお、法改正により2022年5月以降は厚生年金被保険者であれば65歳になるまでiDeCoに加入できるようになります(従来は60歳まで)。
また、DCの老齢一時金に関しては、退職一時金やDBの一時金とは異なる税制上の扱いがあります。それは、退職の有無にかかわらず退職所得になるという点です。これは、そもそもDCの老齢給付金の受給要件が退職(資格喪失)ではなく年齢により定められたことによるものと考えられます。したがって、定年年齢や退職時の年齢に関係なく、DCの老齢一時金は常に退職所得として扱われます。
さらに、DCの老齢一時金については「一つの退職に起因して複数の退職所得がある場合、このうち最初に支払われるものの属する年の収入とする」というルールも適用されません。これも、DCの老齢給付金の支給がそもそも退職に起因するものではないことが関係しているのでしょう。したがって、会社から退職一時金の支給があった年の翌年以降にDCの老齢一時金を受け取った場合、老齢一時金は実際に支給される年の退職所得として扱われます。これにより、同じ年に受け取る場合よりも税負担が減少する場合があります(詳しくは「確定拠出年金の受け取りは1年ずらした方が節税になる」を参照)。なお、法改正により2022年4月以降は75歳までDCの老齢給付金の支給を遅らせることが可能となります(従来は70歳まで)。
制度ごとの退職所得の扱いのまとめ
ここまでに解説した各制度からの一時金について、退職所得としての扱いをまとめると、以下の表のとおりとなります
| 退職一時金 | DB一時金 | DC一時金 | |
| 退職所得となるもの (原則的な扱い) |
退職に起因して一時に支払われるもの | 同左 | 老齢一時金 |
| 旧定年で支給される退職金相当の一時金 | 相当の理由があると認められるものは退職所得(該当しない場合は給与所得) | 相当の理由があると認められるものは退職所得※1(該当しない場合は一時所得) | 老齢一時金であれば退職所得 |
| どの年の退職所得になるか? | 給付事由が生じた(退職した)年※2 | 給付事由が生じた(退職または一時金を選択した)年※2 | 老齢一時金が支給される年 |
※1:退職一時金がある場合はそれも併せて旧定年で支給されることも要件となる
※2:同じ退職に起因する退職所得が複数ある場合は、このうち最初に支払われるものの属する年の退職所得となる
複数制度の退職所得がある場合の考え方
最後に、複数制度の退職所得がある場合の扱いについて解説します。退職一時金とDB、DCなど複数の退職給付制度がある場合やiDeCoにも加入している場合は、退職所得となる一時金の支給が複数発生します。この場合の退職所得の計算の考え方は次のようになります。
【同一年に複数の退職所得がある場合】
一時金支給額の合計額から退職所得控除額を差し引いた残額の1/2をその年の退職所得とする。このときの退職所得控除額の計算に用いる勤続年数は各制度の勤続年数(加入者期間)を合算した年数となるが、重複した期間は除かれる。
<計算例>
・ 40歳から65歳まで25年間勤務した会社から、65歳退職時に退職一時金を受給
・ 35歳から60歳まで25年間加入したDCの老齢一時金を65歳時点で受給
上記のケースにおける退職所得控除額の計算に用いる勤続年数は35歳から65歳までの30年間であり、退職所得控除額は800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
【前年以前に他の退職所得がある場合①】
・ DCの老齢一時金以外の退職所得について、他の退職所得が前年までの4年間より前の場合
・ DCの老齢一時金による退職所得について、他の退職所得が前年までの19年間(注)より前の場合
注:DC老齢一時金の支給時期が2022年4月より前の場合は14年間。以下同じ
上記のケースでは、前年以前の退職所得と勤続年数の重複があったとしても、それを考慮することなく退職所得控除額を計算します。例えば、60歳到達時にDCの老齢一時金を受給し、その後65歳到達時に会社から退職一時金の支給があった場合、DCの加入者期間と退職一時金の勤続年数に重複があったとしても、退職一時金に関しては勤続年数をそのまま退職所得控除額の計算に用います。
【前年以前に他の退職所得がある場合②】
・ DCの老齢一時金以外の退職所得について、他の退職所得が前年までの4年以内である場合
・ DCの老齢一時金による退職所得について、他の退職所得が前年までの19年以内である場合
上記のケースでは、前年以前の退職所得との勤続年数の重複が考慮されます。以下に計算例を2つ示します。
<計算例1>
・ 40歳から60歳まで20年間勤務した会社から、60歳退職時に1,000万円の退職一時金を受給
→この時の退職所得控除額は40万円×20年=800万円となって退職一時金額よりも小さいため、控除額の全額を使い切ることになります。
・ その後、45歳から65歳まで20年間加入したDCの老齢一時金を65歳時点で受給
→もし前年以前に他の退職所得がなければ、退職所得控除額は40万円×20年=800万円となります。しかし、45歳から60歳までの15年間は60歳時点で支給された退職一時金の勤続年数と重複しているため、この期間に対する退職所得控除額600万円(=40万円×15年)が差し引かれ、残りの200万円がDCの老齢一時金に対する退職所得控除額となります。
<計算例2>
・ 40歳から60歳まで20年間勤務した会社から、60歳退職時に600万円の退職一時金を受給
→この時の退職所得控除額は40万円×20年=800万円となって退職一時金額よりも大きいため、控除額に使い残しがある状態です。実質的な控除額(600万円)に対応する勤続年数は15年(=600万円÷40万円)となります(1年未満の端数が生じた場合は切り捨てる)。
・ その後、45歳から65歳まで20年間加入したDCの老齢一時金を65歳時点で受給
→計算例1と同様に、60歳時点で支給された退職一時金の勤続年数との重複を差し引いて退職所得控除額を計算します。しかし、この場合の退職一時金の勤続年数は実際の勤続年数ではなく、上記の実質的な控除額に対応する勤続年数である15年(40歳から55歳)として考えます。そのため、重複期間は45歳から55歳までの10年間となり、重複期間に対する退職所得控除額は40万円×10年=400万円となります。したがって、DCの老齢一時金に対する退職所得控除額は800万円-400万円=400万円と計算されます。
また、上記①(退職所得控除の計算において勤続年数の重複を考慮しなくてよいケース)に該当する条件を改めて整理すると、下記(1)または(2)のとおりとなります。
(1) 60~70歳で在職のままDCの加入資格を喪失して老齢一時金を受給し、その翌年から数えて5年目以降(早くても65歳到達年)に会社を退職して退職一時金等を受給した場合(例えば、定年年齢を65歳として退職一時金の支給時期も65歳としつつ、DCは60歳資格喪失とした場合に該当するケースが発生する)
(2) 55歳以下で会社を退職して退職一時金等を受給し、その翌年から数えて20年目以降にDCの老齢一時金を受給した場合(DCの老齢一時金は遅くとも75歳に受給する必要があるため、56歳以降の退職一時金等についてはこの条件を満たさない)
注:DC老齢一時金の支給時期が2022年4月より前の場合は「20年目」を「15年目」、「75歳」を「70歳」に読み替え
著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長
1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。
出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう
労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。
シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。