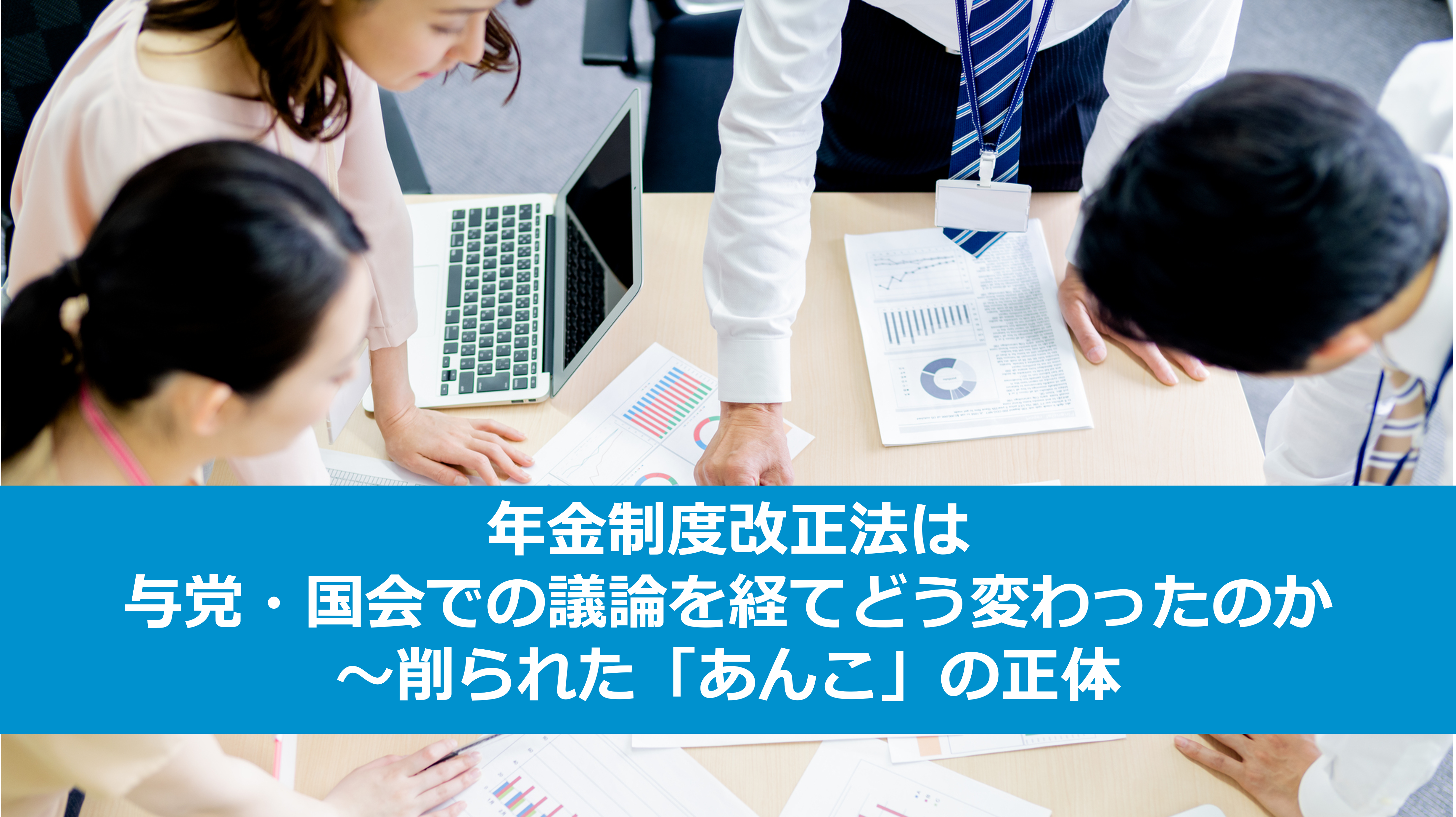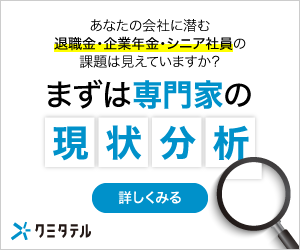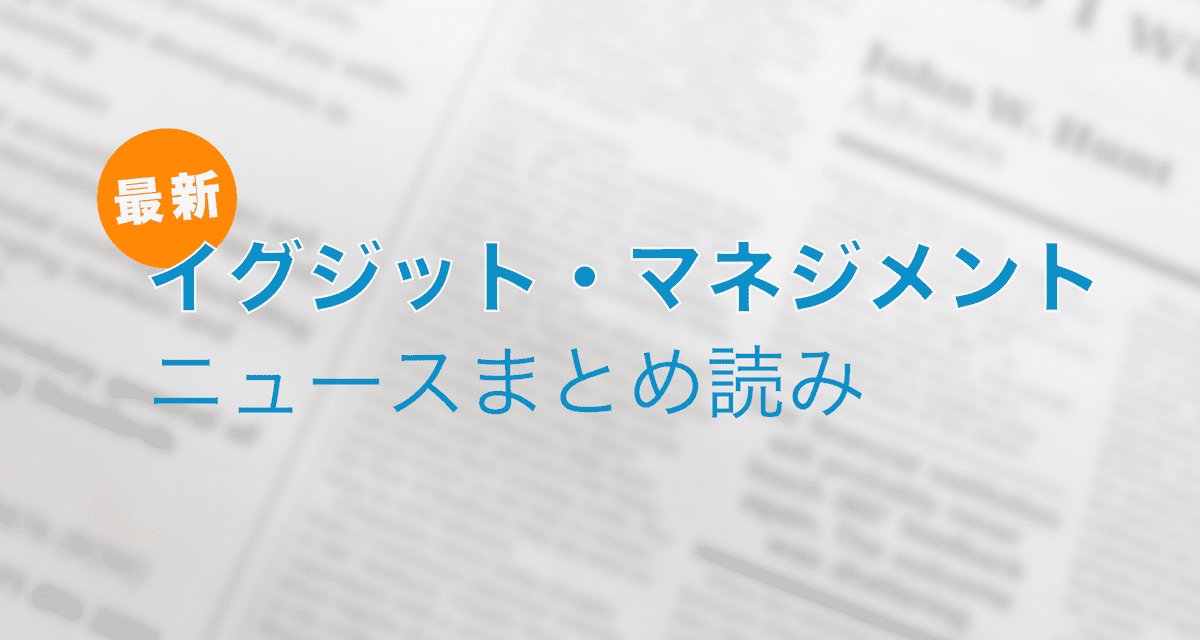【専門家解説】年金運用で 17 兆円もの損失を出してもなぜ公的年金は維持可能なのか?

こんにちは、株式会社クミタテルの退職金専門家 向井洋平です。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、世界的に株価が大きく下落しています。公的年金の積立金を運用する GPIF (年金積立金管理運用独立行政法人) の 2020 年 1 ~ 3 月期の運用損失は 17 兆円程度の見込みであると報道されています。率にすると 10% 程度のマイナスです。
これだけの運用損失が出ると年金制度にとって大きな打撃になりそうですが、公的年金に関してはそのようなことはありません。なぜそう言えるのか、また、ほかの年金制度についてはどうなのか、まとめてみました。
公的年金の積立金は年金給付額の 3 年分に過ぎない
GPIF が運用する積立金の総額は 2019 年 12 月末時点で 168 兆 9,897 億円と、具体的にイメージするのが難しいほどの大きな金額ですが、実は、これは厚生年金・国民年金(基礎年金)として支給される年金額のおよそ 3 年分に過ぎません。つまり、仮に積立金の取り崩しだけで年金給付を賄っていくと 3 年で底をついてしまうということです。
しかし実際には、公的年金の財政は 100 年後においても年金給付額の概ね 1 年分の積立金を確保できるように運営されています。今と 2 年分しか変わらない水準です。では残りの 98 年分の資金はどこから賄っているのかというと、そのほとんどは現役世代が負担する保険料とすべての世代が負担する消費税です。ですから、現在の積立金の運用で一時的に 10% 程度のマイナスが出たとしても大勢に影響はないのです。これは積立金の運用が非常に良かった場合でも同じです。
このように、毎年の年金給付をその年の保険料収入で賄っていく年金制度の財政方式を賦課 (ふか) 方式と呼びます。完全な賦課方式ではそもそも積立金は存在しません。日本では、少子高齢化により人口の年齢構成がアンバランスになっていることから、完全な賦課方式にしてしまうと現役世代の負担が重くなりすぎます。そのため、賦課方式を基本としつつも積立金を運用しながら少しずつ取り崩して給付に充てていくことで、アンバランスの解消を図っています。
GPIF は非常に長期にわたる積立金の運用期間において必要な利回りを最低限のリスクで確保することを運用の目標に置いており、短期的な損失を出さないことを最優先に考えているわけではありません。この 3 ヶ月間では 17 兆円程度の損失が見込まれますが、市場での運用を開始した 2001 年度以降の累積では 2019 年 12 月末時点で 75.2 兆円の収益を確保しています。2020 年 3 月末時点でも通算の収益率は目標とする利回り (名目賃金上昇率を差し引いた実質で年 1.7%) を十分に上回っていると考えられ、今回のような短期的な損失は「最低限のリスク」の範囲内であると考えてよいでしょう。
公的年金とは対照的な企業年金連合会の通算企業年金の運用
上記のように、公的年金は賦課方式を基本とした財政運営を行っているため、積立金の運用損益が財政に与える影響は良くも悪くも限定的です。公的年金が賦課方式を採用できるのは、国民全体を対象とした強制加入の年金制度だからです。出生率などによって左右される側面はあるものの、現役世代からの保険料収入を将来にわたって確実に見込むことができます。
これに対して、任意加入の私的年金制度 (企業年金や個人年金) では賦課方式が採用されることはまずありません。何らかの事情により加入者が新たに入ってこなくなったり、制度を終了しなければならなくなったりしたときに、賦課方式ではその後の給付が支払えなくなるからです。外部に資金を積み立てない退職一時金制度はある意味賦課方式によって運営されている制度であり、企業が倒産したときには退職金が支払われる保証はありません。
そうした観点で公的年金と対照的な財政運営を行っているのが企業年金連合会の通算企業年金です。通算企業年金は、確定給付企業年金を中途で脱退したり、制度終了によって確定給付企業年金の加入者でなくなった人などから資金を受け入れ、65 歳以降に終身年金給付を行う制度です。通算企業年金に掛金収入 (公的年金の保険料に相当する収入) はなく、受け入れた資金とその運用収益だけで将来の年金給付を賄っていく必要があるため、公的年金とは違って運用損益は財政状況に大きな影響を与えます。
そのため、通算企業年金の積立金の運用は GPIF よりも安全性を重視した内容となっており、目標とする利回りもそれだけ低くなっています。また、年金給付はその目標利回りに応じて計算された額となります。具体的には、GPIF の運用方針では積立金の半分を株式に投資することとしていますが、通算企業年金では株式への投資割合を 2 割にとどめています。
企業年金連合会では四半期ごとの運用状況の公表は行っていないため詳細を把握することはできませんが、資産構成などから推計すると 2020 年 1 ~ 3 月の期間収益率は 4% 前後のマイナスにとどまっているものと考えられます。2019 年 3 月末時点の通算企業年金の積立金は、将来の年金給付を賄うために必要な金額(責任準備金)を 10% 以上上回っており、今回の運用損失によっても積立不足に陥っている可能性はほぼないと考えられます。
通算企業年金のように新たな掛金収入が入ってこない年金制度では一度大きな積立不足を抱えてしまうと回復させるのが難しく、給付を削減するか、積立不足が拡大するリスクを負ってでも積極的な運用に賭けるほかありません。公的年金の積立金の半分が株式に投資されていることを「博打」などというメディアもありますが、博打とはこのような状況において用いるべき表現でしょう。
苦しい状況に追い込まれている国民年金基金
上記のとおり、企業年金連合会の通算企業年金は掛金収入がないという状況の中でも安定的な財政運営を行っていますが、これに対して非常に苦しい状況に追い込まれているのが国民年金基金です。国民年金基金は国民年金の第 1 号被保険者 (自営業者等)を対象とした制度であり、厚生年金がない第 1 号被保険者に対して国民年金 (基礎年金) に上乗せする形で終身年金給付を行う制度です。「国民年金」と名の付く公的な制度ですが、強制加入ではなく本人の意思により任意に加入する制度であることから私的年金 (個人年金) に分類されます。
国民年金基金制度は、47 都道府県別に設立された地域型基金、25 の職種ごとに設立された職能型基金、および各基金を中途脱退した加入員に対して年金給付を行う国民年金基金連合会によって運営されていますが、掛金や給付の内容は全基金同じです。なお、2019 年 4 月にはすべての地域型基金と 22 の職能型基金が合併して「全国国民年金基金」となりました。以下、加入員数等の各数値および金額については全基金を合計したものとしています。
国民年金基金の加入員数 (掛金を納付している人) は 1991 年の設立以降しばらくは増加傾向にありましたが、2003 年度末の 78.9 万人をピークにその後は減少を続けており、2018 年度末には 36.3 万人にまで減少しています。その一方で年金受給者数は 2018 年度末で 59.8 万人と加入員数を上回っており、今後さらに増加していくことが見込まれます。また、新規加入員は 2004 年度以降毎年 2~3 万人程度で推移していますが、国民年金基金の加入対象である第 1 号被保険者自体が年々減少していることなどから、今後新規加入員が大きく増えていくとは考えにくい状況です。
国民年金基金連合会が公表している年金財政の推移によると、2018 年度はプラスの運用収益だったにもかかわらず年度末の純資産額は前年度より減少しており、年金給付が掛金収入を上回る状況にあると考えられます。
つまり、国民年金基金の財政は運用収益に依存する構造となっており、本来であれば企業年金連合会の通算企業年金と同様に、安定的な運用によって積立不足を回避できるような運営を行っていく必要があります。しかし実際には長らく積立不足の状況が続いており、責任準備金に対する実際の積立比率は 2018 年度末時点で 80% となっています (20% の積立不足)。計画上の利回りも高めの設定となっていることから、必要な収益を確保するために公的年金と同様に積立金のおよそ半分を株式に投資しています。そのため、運用実績 (利回り) は公的年金と同じような水準で推移しており、今回発生した運用損失により積立不足は拡大しているものと考えられます。
今の状況では国民年金基金の財政を回復させ安定的に運営していくのは非常に困難と言わざるを得ず、制度の存廃も含めた抜本的な見直しを考えなければならない時期に来ているといえるでしょう。
著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長
1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。
出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう
労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。
シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。