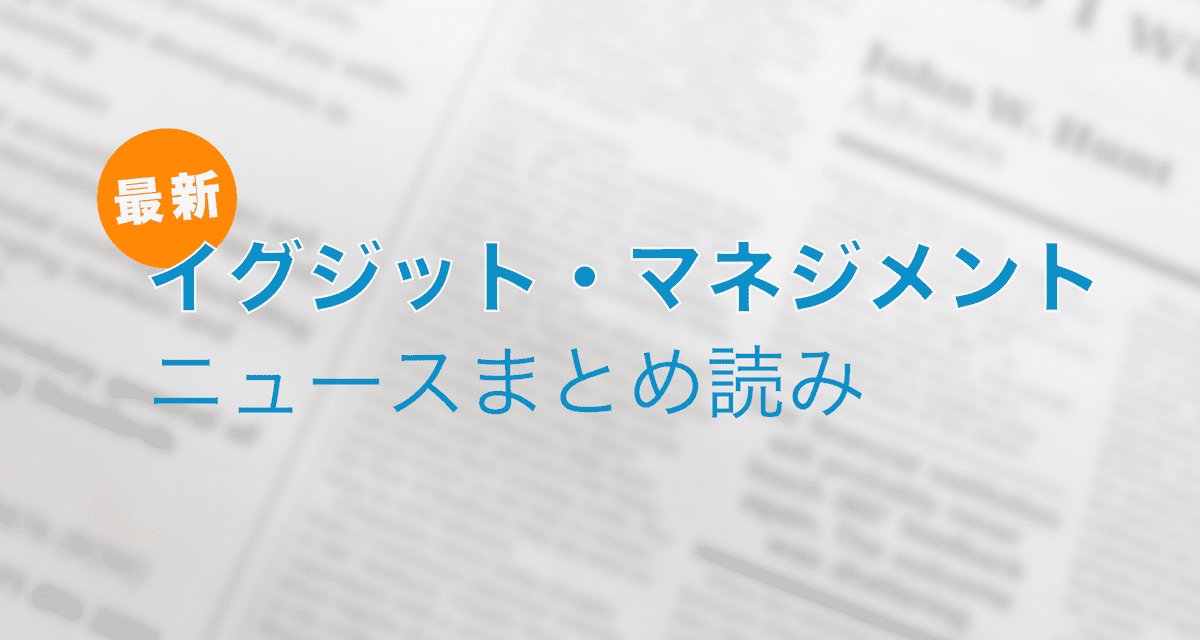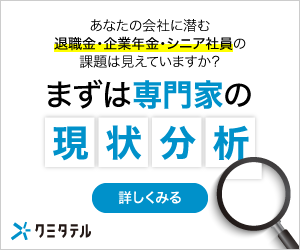【人事必見】死亡率に応じた年金額の自動調整の仕組みと影響
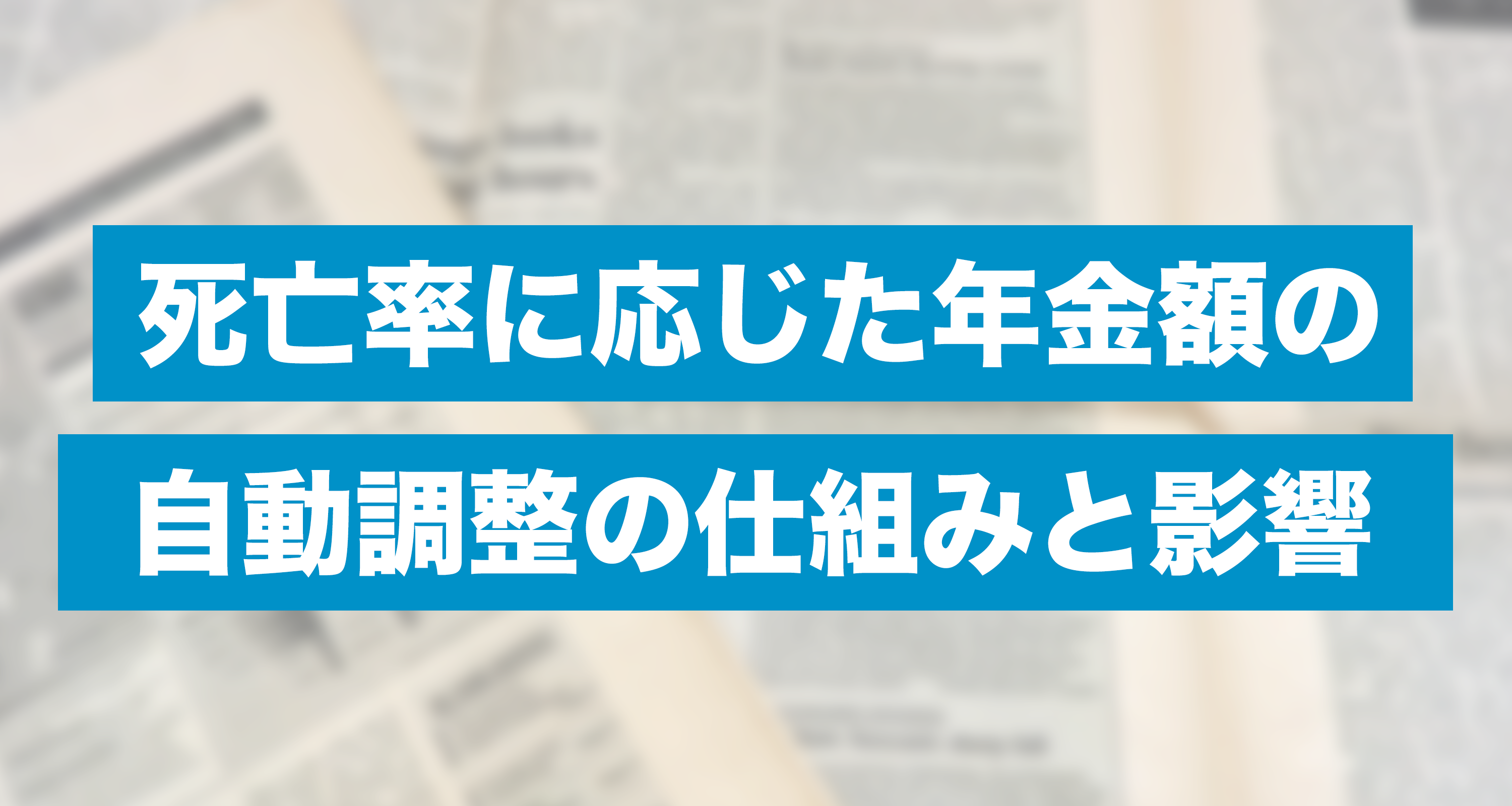
2 月 14 日の日経新聞朝刊 1 面トップに「企業の終身年金、支給抑制可能に」の記事が掲載されました (電子版はこちら)。平均余命の伸びに応じて、年金支給額を自動的に調整する仕組みが導入可能になるという趣旨の内容です。
この仕組みは、もともとは厚生労働省の企業年金・個人年金部会において年金数理人会から提案されたものです。2019 年 12 月 25 日に取りまとめられ公表された「議論の整理」にも、確定給付企業年金に関する改正事項の 1 つとして盛り込まれています。
<参考>企業年金・iDeCoはこう変わる~企業年金・個人年金部会で示された改正案
本改正の実現には省令改正が必要であり、その詳細や施行時期についてはまだ明らかになっていませんが、改正の背景や現時点で想定される具体的な改正内容、及びその影響について解説します。
長生きにより増える終身年金の企業負担
現在実施されている確定給付企業年金の多くは、支給する年金の期間が 10 年、15 年、20 年といった一定の年数で定められています。こうした年金は確定年金 (あるいは有期年金) と呼ばれ、長生きしても一定の年数がたてばそこで支給は終了します。一方、支給期間中に死亡した場合は残りの年数に応じた金額が遺族に支給されるため、平均余命の長短は企業の負担にほとんど影響しません。そもそも確定年金の制度では、年金受取ではなく一時金受取を選択する割合が総じて高くなっています。
これに対して、一部の企業 (主に大企業) で実施されている確定給付企業年金では終身年金が支給されています。ほとんどの場合、終身年金には 10 ~ 20 年の保証期間が付いており、受給開始時または受給開始後に一時金での受け取りを選択した場合、あるいは保証期間内に死亡した場合は、保証期間の年金に相当する金額 (すでに支給済みの部分を除いた額) が支給されます。保証期間が過ぎた後は長生きした分だけ年金を受け取ることができるため、終身年金の制度では年金受取の選択割合が高い傾向にあります。
企業側から見ると、確定年金とは異なり、終身年金の場合は平均余命が延びることによって負担は増えていきます。確定給付企業年金では掛金計算などの基準となる死亡率が 5 年ごとに見直されており、2020 年度からは新たな死亡率が適用されます。死亡率の低下によって企業の負担がどの程度増えるのか、パブリックコメントで公表されている新死亡率をもとに、一定の前提をおいて試算すると以下のようになります。
<前提条件>
・支給開始年齢:60 歳
・支給期間:20 年保証期間付き終身
・予定利率:2.0%
<試算結果>
年金額 1 に対して支給開始時点で確保しておくべき原資は、
・現行死亡率のもとでは 20.121
・新死亡率のもとでは 20.427 … 1.5%の増加
※いずれも男性の死亡率により計算。
今後も同じようなペースで平均余命が延びていくと、企業が確保しておくべき原資は 5 年ごとに 1 ~ 2%ずつ増え続けていくことになります。
死亡率に応じた年金額の自動調整の仕組みと年金額への影響
こうしたことから、平均余命が延びても企業の負担を増やすことなく終身年金を維持できるように考えられたのが今回の仕組みです。上記の試算の例でいうと、死亡率の低下に応じて、保証期間が終了した後の 80 歳以降の年金額を減らすことで、企業の負担が増えないようにします (逆に、死亡率が上昇した場合は年金額を増やすことになり、企業の負担は減らない)。
具体的には、現行死亡率での 80 歳以降の年金額が 80 歳までと同じ水準だとすると、新死亡率のもとでは 80 歳以降の年金額をおよそ 8 %減額することで、60 歳時点で企業が確保しておくべき原資は不変となります。80 歳時点で比較した場合には、およそ 3 %の減額で同等となります。どの時点を基準として年金額を調整することになるのかは現時点では明らかではありませんが、いずれにしても、保証期間が終了した後の年金額については、 5 年に 1 回の死亡率の見直しごとに変わっていくことになります。
ちなみに、上記1.で試算した「確保しておくべき原資」の増加率よりも、年金の減額率のほうが大きくなっているのは、保証期間内 (80 歳まで) の年金額は変わらないためです。
制度の導入手続き
仮に制度改正によって今回の自動調整の仕組みが実現したとしても、それを導入するかどうかは終身年金を実施している各企業の判断です。また、制度の導入には規約変更の手続きが必要となります。
確定給付企業年金で給付減額を伴う規約変更を行うには、次の 2 つの要件をクリアしなければなりません。
① 理由要件
規約変更を行う理由が、就業規則等の変更に伴って給付設計を見直す場合や経営状況の悪化による場合など、省令に定められた要件に合致すること
② 手続き要件
規約変更について加入者の 2/3 以上の同意を得るなど、省令に定められた同意手続きを経ていること
ところで、給付設計を変更した場合にそれが給付減額に該当するかどうかは、変更前後で給付の見込み額の現在価値が減少するかどうかで判断されます。このとき、死亡率を含む計算基礎率は同一のものを使用して比較することとなっています。したがって、現行のルールでは死亡率による自動調整の仕組みを導入しても給付減額には該当しないこととなります (死亡率が同一であれば年金額も変わらないため)。
しかし、死亡率は今後も低下傾向が続くことが見込まれており、実質的には減額となる可能性が高いといえます。冒頭の日経新聞の記事では「加入者の 3 分の 2 の同意」が条件とされており、導入には給付減額の場合と同様の手続き要件が課されることが想定されます。一方で、経営状況の悪化等の理由要件までは求められないと想定されます。また、自動調整の対象となるのは基本的に規約変更時点の加入者に限られるものと考えられます (すでに退職している年金受給者は自動調整の対象外)。
退職給付債務への影響
終身年金を実施している企業が今回の自動調整の仕組みを導入した場合、退職給付債務への影響はどうなるでしょうか。
多くの場合、退職給付債務の計算には、確定給付企業年金の基準死亡率と同一の死亡率が用いられています。そのため、死亡率による年金額自動調整の仕組みを導入しても、その時点では退職給付債務は変動しません。ただし、その後死亡率が改定され低下した場合の退職給付債務の増加は抑えられることとなります。
一方で、IFRS (国際会計基準) では原則として将来の死亡率の改善 (低下) を織り込んで計算することとされています。つまり、将来見込まれる平均余命の延びがすでに債務の額に上乗せされている状態になっています。そのため、IFRS適用企業では制度導入時点で将来の年金額の調整 (減額) を反映することで、退職給付債務は減少すると考えられます。このとき、マイナスの過去勤務費用が発生することで、一時的に利益を押し上げる要因となります。
死亡率による年金額の自動調整は導入すべきか
今回の制度改正が実現することで、終身年金を実施する企業にとっては今後の対応の選択肢が 1 つ増えることになります。例えば、定年延長等により 60 歳以降の処遇を改善しつつ、企業年金については自動調整の導入により負担を軽減するといったことが考えられます。
ただ、自動調整の対象となるのは基本的にその時点の加入者です。実際に支給される年金額に反映されるのは、退職して年金を受け取り始め、保証期間を経過したあとからになります。上記1.の試算の例でいえば 20 年以上先です。それよりも長い期間、将来にわたって終身年金を維持するつもりがなければ、この制度を導入する意味はないでしょう。
年金額の自動調整により平均余命の伸びによる負担増を抑えることはできても、終身年金である限りは受給者が亡くなるまで制度に残り続けることに変わりはありません。終身年金の維持には財務的な体力や制度運営体制を保持していくことが必要となります。制度導入の際には、いつ、どのような影響 (効果) が出るのかを定量的に把握し、他の様々な選択肢との比較検討を行ったうえで意思決定すべきでしょう。
著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長
1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。
出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう
労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。
シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。