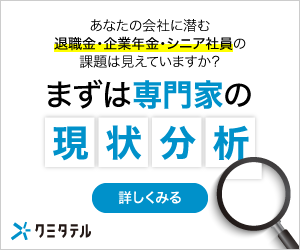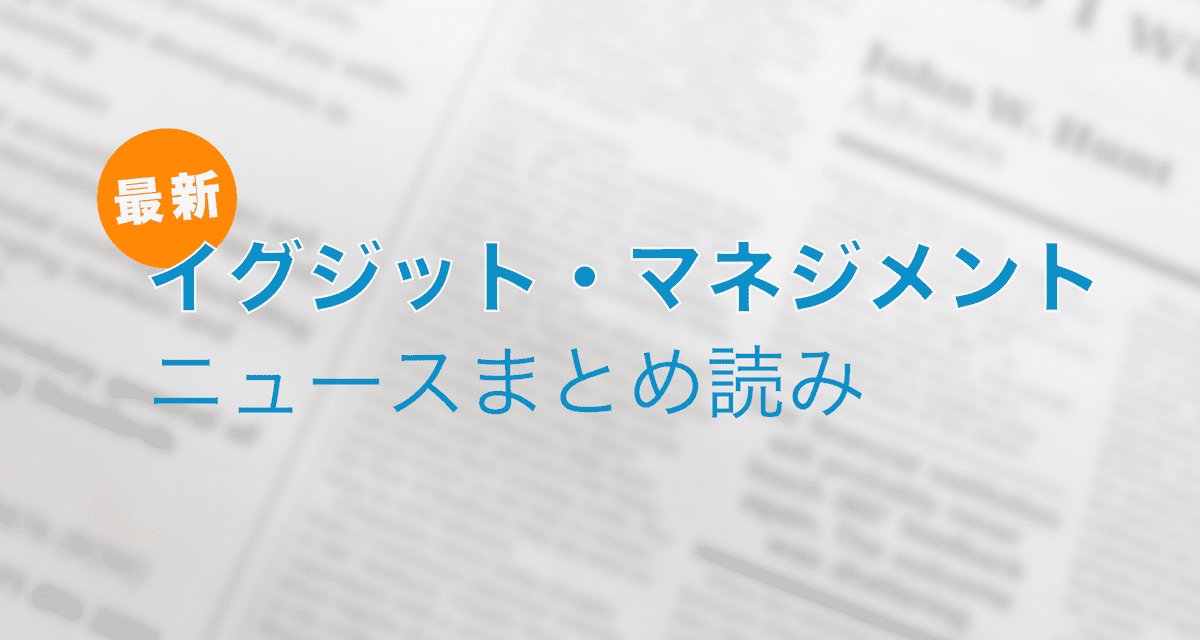【人事担当者向け】メンバーシップ型からジョブ型への移行で退職金制度はどう変わるのか
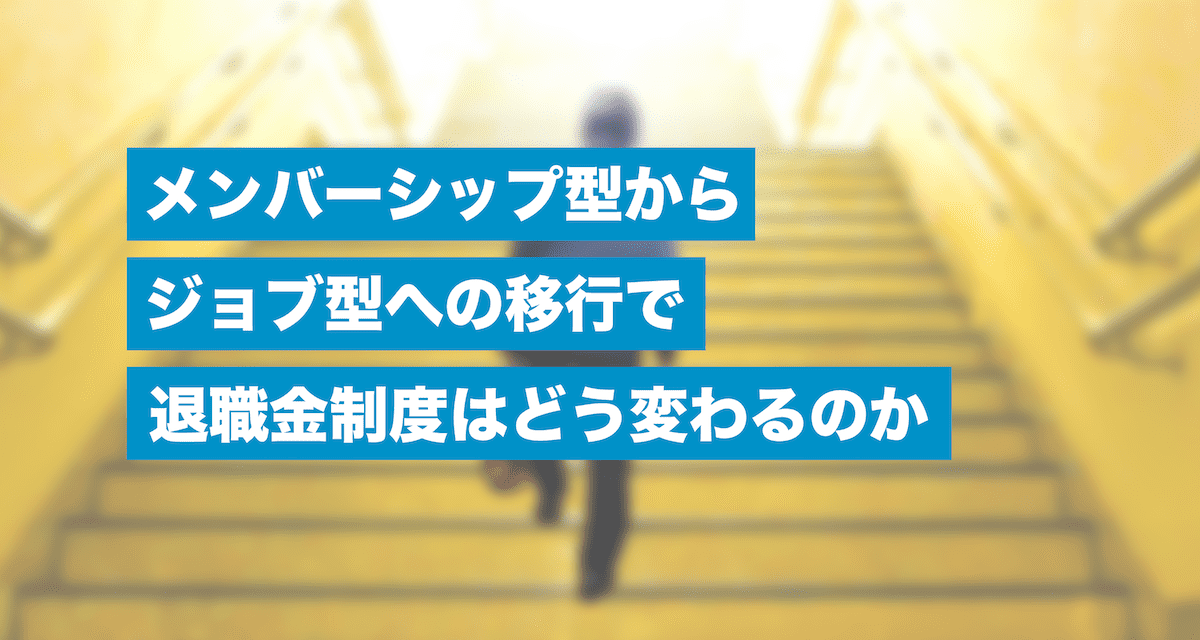
昨今、企業人事では「ジョブ型」への関心が非常に高まっています。これは、グローバル化の進展や少子化による人材獲得競争の激化、高齢化・長寿化による就労期間の延伸などを背景として、日本特有の「メンバーシップ型」の弊害や限界があらわになってきたことの裏返しともいえます。メンバーシップ型が根付いてきた日本社会においてジョブ型への移行が全面的に進むとは考えにくいですが、いくつかの側面からジョブ型の考え方や要素を取り入れる動きは進んでいくでしょう。そうしたときに、退職金制度のあり方や制度設計はどのように変わっていくのでしょうか?メンバーシップ型における退職金制度の特徴と対比しながら考えていきます。
定年退職モデルからの脱却
企業の退職金水準は「定年退職時の退職金額」によって表され、モデル退職金といえば入社から退職までの標準的な退職金額の推移を指すのがこれまでの考え方でした。この考え方は、2つの意味でメンバーシップ型の人事システムが前提になっています。
1つは新卒で入社して定年まで同じ会社に勤めることを想定していること、もう1つはモデル退職金のもととなる社内での昇給や昇格のモデルが存在しているということです。
ジョブ型では事業運営に必要なポスト・職務に空きができたときにその都度即戦力の人材を調達するというのが基本的な考え方です。したがって、職務経験のない社員を採用して社内で育成し、昇格していくという「標準モデル」は存在しません。また、一律の年齢で退職させる定年制もジョブ型の考え方にはそぐわないものです。実際、ジョブ型が一般的な海外では定年制のない国も多いです。
それでは、入社時期や退職時期が一定せず、社内の標準的な昇格モデルも存在しないときに、退職金の金額や水準は何を基準に考えるべきでしょうか。
ジョブ型人事制度では、職務レベルをランク付けした職務等級(ジョブグレード)を定め、等級ごとに報酬(職務給)の水準が定められます。退職金も報酬の1つと位置づけ、等級ごとに1年あたりの退職金の付与額(積み上げ額)を定めるのが整合的な考え方になります。具体的には、職務等級に基づくポイント制により設計された退職金制度がこれにあたります。
キャリアパスが一様でなくなるジョブ型では、最終的な退職金額でモデルを設定することはできません。給与水準を年収で見るのと同じように、職務レベルに応じた1年あたりの付与額という視点で退職金の水準を設定していくことになります。
退職事由や勤続年数による不合理な格差の解消
日本企業の退職金制度では、定年退職や会社都合退職では基準額の100%が支給されるのに対して、自己都合退職では支給額が減額される設計がよく見られます。極端なケースだと、勤続年数が30年以上でも定年直前に自己都合退職すると支給額が半分になるような設計もあります。また、勤続10~20年目あたりまで退職金額を低く抑え、その後金額を大きく積み増していくような設計もよく見られます。
これらは、新卒採用した社員を長期に(定年まで)雇用することを前提としたメンバーシップ型の考え方を反映したものです。社員が早期に離職してしまうと採用や育成のコストが回収できないので、短い勤続年数では退職金の支給を抑えるという側面もあるでしょう。
しかしジョブ型ではその時々の職務レベルに応じた給与を支払い、退職金を付与していくことになります。退職事由によって支給額に差を設けたり、年齢や勤続年数によって付与額に格差を設けるのは合理的ではありません。
米国では、従業員の退職所得について定めたエリサ法において、一定の勤続年数(5年または7年)等の要件を満たす労働者に対しては100%の受給権を付与し、早期退職や懲戒解雇の場合であっても没収されないことが規定されています。また、長期勤続を過度に優遇するような給付設計を制限しています。その背景には長期勤続優遇を規制して労働の流動性を確保するという考え方があり、職務要件を満たす人材を労働市場から調達するジョブ型と整合的になっています。
ポータビリティと離転職資金のバランス
新卒で入社した会社に定年まで勤めるというメンバーシップ型のキャリアモデルが崩れたとき、退職金制度が備えるべき機能は大きく2つに分かれます。1つは老後(引退後)に備えた資金準備であり、離転職の際に払い出しせず他の制度に資金を移して積み立てを継続できるようにすること(ポータビリティ)です。もう1つは離職時の自由資金であり、再就職や学び直し、独立開業など次のキャリアに進むために必要な資金を提供することです。
「退職=引退」と考えるメンバーシップ型ではこれら2つの機能をあえて分ける必要性はありませんが、ジョブ型に移行する際にはこれらのバランス考慮しながら退職金制度の設計を考えていく必要があるでしょう。
例えば、退職金の支払原資を社内で準備する退職一時金は退職時に一括して支払われ、ポータビリティの機能はありません。これに対して、確定拠出年金は老後資金準備のための制度として明確に位置付けられており、原則として60歳未満では引き出しができない代わりに職業にかかわらずポータビリティが確保されています。また確定給付企業年金では、退職時の支払いが認められているのに加えて、本人の選択により確定拠出年金等の他の制度へ資金を移すことも可能となっており、柔軟性が確保されています。こうした制度ごとの特徴を踏まえ、退職金制度の構成を考えていくことになります。
退職金でなくてはならない理由はない
ここまで、メンバーシップ型からジョブ型に移行したときに退職金がどのように変わるかを考えてきましたが、その時々の職務の対価として報酬額を決めるのであれば、そもそも退職金という形で報酬を支払う必要性はないともいえます。退職金として付与していた分を給与に上乗せし、あとは個人がそれぞれの判断でその一部を老後資金準備としてiDeCo(個人型確定拠出年金)に積み立て、一部を必要な時にいつでも引き出せる貯蓄に回すことでもよいわけです。
ただ企業年金法制や税制の観点からは、退職金・企業年金制度を活用したほうが、より効率的に退職時や引退後の資金を準備することができます。この点はジョブ型であろうとメンバーシップ型であろうと変わりません。
したがって、企業としては退職金制度を用意したうえで、その利用については従業員の選択に任せるという方向性が考えられます。具体的には、毎期の退職金の付与額を確定拠出年金や確定給付企業年金に積み立てるのか、前払い(給与への上乗せ)で受け取るのかの配分を、本人が選択できるような仕組みがあります。ジョブ型では従業員のキャリアが多様化しますから、そうした観点からもそれぞれの状況に応じて受け取り方を選択できるのは望ましいことです。
まとめ
冒頭で述べたように、日本企業でメンバーシップ型からジョブ型への移行が一気に進むとは考えにくいですが、画一的なキャリアやそれを前提とした処遇体系の見直しは徐々に進んでいくでしょう。それに伴って、退職金に対する考え方や制度設計は以下のように変わっていくと考えられますし、実際、最近の退職金制度の見直しではこうした傾向が見られます。
・ 「定年時の支給額」から「1年あたりの付与額」への転換
・ 付与額は年齢や勤続年数ではなく職務レベルにより決定
・ 自己都合退職による減額の緩和、解消
・ 「ポータビリティ」と「離職時の資金」のバランスを考慮した制度構成
・ 「退職金・年金」か「給与」かは従業員が選択
著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長
1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。
出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう
労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。
シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。