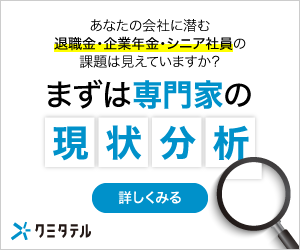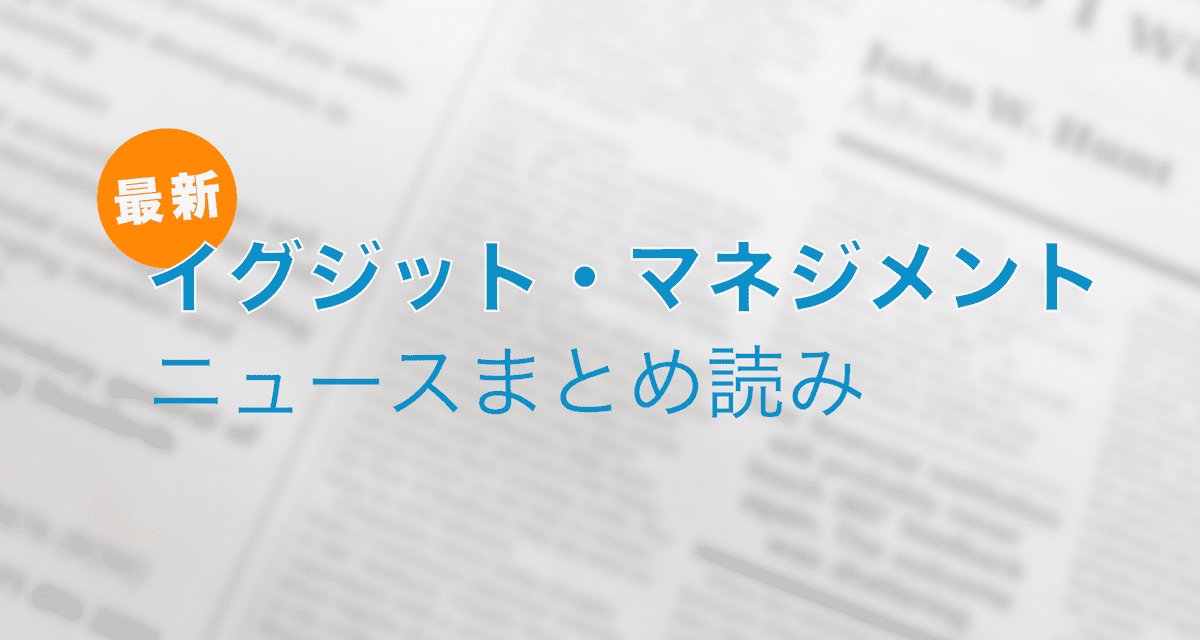退職金は「縮小」か「充実」か? 報酬配分を適正化し、人材獲得・定着を実現する戦略的アプローチ

近年、採用の売り手市場や物価上昇を背景として、賃上げなどの従業員の処遇改善を行う企業が多くなっています。そうした中で、退職金制度についてはどう考えればよいでしょうか?まずは退職金制度の新規導入や見直しを行ったいくつかの例を見てみましょう。
なお、以下の事例はいずれも当社の支援実績に基づくものですが、趣旨が変わらない範囲で一部修正・加工しています。
事例1:企業型DCの新規導入によりエンジニアの資産形成手段を提供
システム開発を主な事業をしているA社では、エンジニアの獲得と定着に課題を抱えていました。小規模なA社には退職金制度がなく、「将来の不安なく長く働ける」という観点では他社より劣後していましたが、世間並みの退職金制度を用意することは財務的にも事務的にも困難な状況でした。
そこで、小規模な企業でも実施可能な企業型DC(確定拠出年金)のプランを探し、既存の給与に追加する形で選択制のDCを新たに導入しました。これにより、社員は税制メリットを生かした老後の資産形成が可能となり、ライフプランや家計の状況によっては掛金の積立に代えて給与に上乗せして受け取ることもできるようになりました。
さらにマッチング拠出も実施することで、本人が希望すれば既存の給与から追加で掛金を積み立てることも可能となり、分散投資により期待される収益を加味すれば、中小企業の平均的な退職金の水準を十分確保できる仕組みを整えました。2026年4月からはマッチング拠出における加入者掛金の制限(加入者掛金は事業主掛金を超えてはならない)が撤廃される見込みであり、資産形成手段としての魅力がさらに増すことが期待されます。
事例2:企業年金の加入により長期にわたる保育園運営への貢献に報いる
保育士の平均的な勤続年数は他の職種と比べて短く、若い年齢での退職が多い業界です。保育園の運営を行っているB社でも同じような状況でしたが、そうした中でも長期に勤続している保育士の社員は重要な存在であり、今後安定的に園を運営していくためには欠かせない人材となっていました。
一方で、捻出できる人件費には限りがあり、経験年数を重ねても給与の伸びは比較的小さいままでした。退職金制度はなく、資産形成手段としての企業型DCも保育所運営という事業の性質から、制度の導入や運用に手間がかかる割に、多くの社員にとってあまり魅力が感じられないものでした。
そこで、勤続5年に達した社員を対象に既存の給与とは別に新たに退職金を積み立てることとし、園長など責任ある立場の社員にはより多くの金額を積み立てることとしました。これにより、長期にわたる保育園運営への貢献に対して退職金という形で報いることができるようになりました。
B社が採用した退職金の積立制度は総合型DB(確定給付企業年金)と呼ばれる企業年金の一形態で、規模も業種も異なる多数の企業が共同で運営する年金基金です。自社で退職金を管理する必要がなく、また、企業型DCと異なり資産の運用と管理は年金基金全体で行われ、年齢にかかわらず退職時にあらかじめ定められた金額を受け取ることができるのが大きな特徴となっています。
事例3:退職金の一部を給与に移行し、全社員の賃上げ原資を確保
地方で自動車部品の製造を行っているC社は近年新卒採用に苦戦しており、特に現場で戦力となる高卒・高専卒の人材を確保するために、初任給の引き上げが急務となっていました。ただ、初任給を引き上げるとそれに合わせて社員全体の給与水準も引き上げる必要があり、原資の確保をどうするかが課題となっていました。
そこで、世間水準と比較しても比較的充実している退職金制度に着目し、将来期間の退職金を一部減額してそれに見合う金額を毎月の給与に一律上乗せすることとしました。そのほか、賞与についてもその一部を毎月の給与に組み入れるなど、報酬構成全体を見直すことで若手社員の月例給与を10%以上引き上げることができました。
ただ、退職金は給与よりも税制面で優遇されているため、退職金の一部を給与に移した場合、額面は同じでも手取りで比べると最終的な受取金額は減ってしまう可能性があります。そのため、制度の見直しにあたっては企業型DCを新たに導入し、退職金から移行した給与の上乗せ部分については、本人の選択によりDC掛金(事業主掛金)に充てることも可能としました。
これにより、税制面の不利益については本人の選択により回避できるようになり、DCの運用状況によっては従来を上回る退職金水準を確保できるようになりました。
処遇改善は報酬配分最適化の好機
上記の事例では、A社は企業型DCにより新たに退職金制度を導入、B社は総合型DBにより新たに退職金制度を導入、C社は既存の退職金を一部減額して給与に移行と、具体的な見直し内容はそれぞれ全く異なります。しかし、必要な人材の獲得・定着という目的は共通しています。言い換えれば、各社とも人材の獲得・定着のために、処遇の改善に合わせて退職金を含めた報酬全体の配分の最適化を図っています。
全体水準を維持したままでの報酬配分の見直しは、どこかを手厚くするためにどこかを削らなくてはなりません。そのため、たとえそれが社員にとっての魅力向上を意図したものであっても、一部が削られることに対する不満を招く可能性があります。変化に対してはメリットよりもデメリットに目が行くのが人間心理です。
従って、処遇の改善と同時に報酬配分の最適化を図ることが重要です。トータルで見た報酬水準が引き上げられるのであれば、仮に部分的に削られる要素があったとしても社員の理解は得られやすいでしょう。
退職給付への配分をどう考えるべきか
それでは、報酬全体の中で退職給付(退職金・企業年金)への配分についてはどう考えるべきでしょうか?そもそも退職給付を設けるかどうかは各企業の任意であり、退職給付制度がない(退職給付への配分を0とする)企業もあります。
しかし、実際には従業員300人以上の企業の約9割、300人未満の中小企業でも7~8割程度が退職給付制度を設けており(※1)、多くの企業では一定割合を退職給付に配分することが人事政策上有効だと考えていることがうかがえます。
その理由として主に考えられるのが次の3点です。
1. 退職給付が用意されていることで、社員が将来に対して無用な不安を持たずに仕事に取り組める
2. 退職給付は給与収入に比べて税制上優遇されており、額面が同じでも手取りが大きくなる(かける人件費が同じなら、退職給付のほうが社員にとって税引後の受取総額が大きい)
3. 退職給付は他の報酬と比べて制度の自由度やバリエーションが大きく、各企業の意図や目的に合わせて設計ができる
そして、退職給付の水準は、定年退職の場合でおよそ「退職時の所定内賃金(月額)×勤続年数」となっています(※1)。つまり、1年間で給与の1ヶ月分を退職金として積み立てているイメージとなります。また、企業が負担している退職金にかかる費用は現金給与総額のおよそ8.7%であり(※2)、やはり給与の1/12程度となっています。
退職給付への具体的な配分を検討する際には、こうした統計データを踏まえつつ、以下のような観点も考慮するとよいでしょう。
・社員のキャリアや意識:社内で長く経験を積むことが求められる事業や職種については退職給付の重要性が大きい。一方で、人材獲得の観点では個人の意識がどう変化しているのか(変化していないのか)も考慮する必要がある。
・生活費に照らした現在の給与水準:今の生活費を十分に賄えるだけの給与水準を確保できていれば、税制等の観点から退職給付を手厚くするメリットが大きい。
・具体的な退職金額の水準:会社が想定する退職者に対して、具体的にどの程度の退職金額を確保しておきたいか。
例えば、上記事例3のケースでは、新卒採用において初任給の水準が大きな課題となっていることから退職金から原資の一部を移行しましたが、移行後も退職金の水準は世間並みを確保することとし、退職金からの移行分で足りないところは賞与から組み換えるなどして対応しました。また、本人の選択により退職金からの移行分をDCに積み立てることも可能とすることで税制メリットも受けられるようにし、世代や個人ごとに異なる意識にも配慮したバランスのとれた対応となっています。
※1:厚生労働省 2023年就労条件総合調査
※2:日本経済団体連合会 2019年度福利厚生費調査結果
* * *
クミタテルでは、個社ごとに異なる状況を踏まえ、必要な人材の獲得・定着に向けた、退職金を含めた報酬配分の最適化を支援しています。限られた原資をどのように配分すべきか、また、配分の見直しを具体的にどう進めるべきかお悩みの企業様は、お気軽にご相談ください。
著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長
1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。