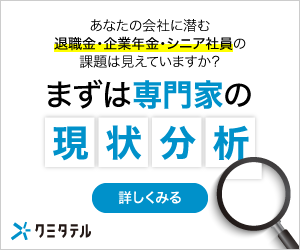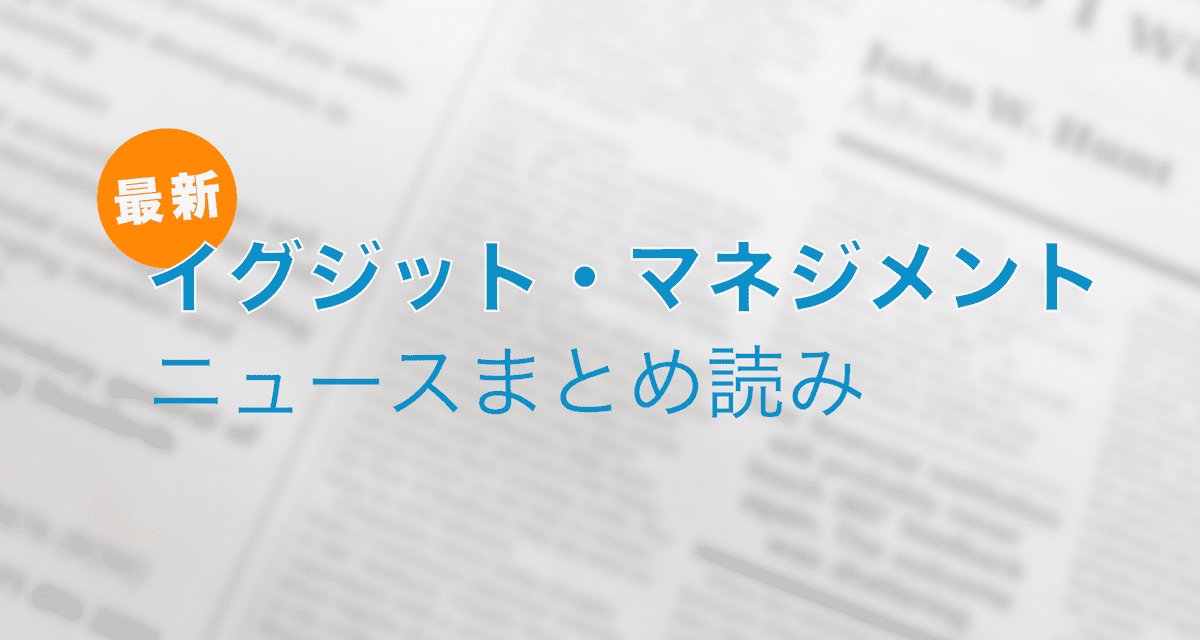【メトロコマース】非正規社員・契約社員への退職金支払いを命じる判決が企業に及ぼす影響

こんにちは、株式会社クミタテルの退職金専門家 向井洋平です。
東京メトロの子会社「メトロコマース」で駅の売店の販売員として働いていた契約社員が、正社員との不合理な労働条件の格差を理由に損害賠償を求めていた裁判で、東京高裁から会社側に退職金の支払いを命じるという注目すべき判決が出されました。
第 1 審の東京地裁では退職金の支払いは認められなかったのですが、東京高裁がどのような考え方で判断を変えたのか、また、この判決内容を踏まえたときに退職金制度を設けている企業にはどのような影響が及ぶのかを解説していきます。なお、筆者は法律の専門家ではなく、あくまで退職金専門家としての見解であることをあらかじめお断りしておきます。
契約社員が訴えた内容
東京メトロ駅構内の売店で販売員として有期雇用契約で働いていた契約社員が、無期雇用の正社員と同じ内容の仕事をしているにもかかわらず、賃金などの労働条件に格差があるのは労働契約法 20 条に違反しているとして、差額分の支払いを会社側に求めたのが今回の裁判です (他にも関連する争点がありましたがここでは省略します)。
労働契約法 20 条というのは、いわゆる同一労働同一賃金の根拠となっている条文であり、2013 年 4 月に施行された改正労働契約法に盛り込まれたものです。
■ 労働契約法 20 条 (期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度 (以下この条において「職務の内容」という。) 、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
この条文を読んで分かるとおり、労働契約法 20 条は、有期雇用社員と無期雇用社員で仕事の内容や責任の程度が同じである場合だけでなく、違いがある場合でも賃金等の労働条件の違いは職務の内容等に照らして不合理であってはならないこと (均衡待遇) を求めています。
今回訴えを起こした契約社員 4 名は、売店での販売業務の内容や責任の重さは正社員と全く変わらず、また契約社員であっても正社員と同様に他部署へ異動した実績があるにもかかわらず、月例賃金、賞与、各種手当、退職金及び褒賞に正社員と違いがあるのは違法であると主張しました。なお、退職金については正社員には支給されるものの契約社員には退職金制度がなく、定年退職であっても退職金は一切支給されていませんでした。
訴えられた会社側の反論
これに対して被告である会社側は、以下のように労働条件の違いに違法性がないことを主張しました。
- 1. 改正労働契約法の施行日は 2013 年 4 月 1 日であることから、それ以前に関しては労働契約法 20 条に基づく請求は成立しない。
- 2. 契約社員と正社員との労働条件の違いは両者の業務内容や責任の違いに基づく合理的なものであって、労働契約法 20 条には反しない。
<会社側が示した業務内容や責任の違い>
- (1) 正社員の業務は売店業務に限られるものではなく多岐にわたっている。売店における販売業務においても、正社員はエリアマネージャー業務や代務の業務に従事するのに対して、契約社員はこれらの業務に従事することはない。
- (2) 固有の売店業務に限ってみても、業務密度に応じた配置の違いがある。売上の多い売店には正社員や契約社員 A (注) を配置しており、原告が勤務していた売店と同規模で最も売上の多い売店では、業務量に3倍の違いがある。
- (3) 契約社員にも商品の発注権限等はあるが、定型的な補充発注にすぎない。
- (4) 正社員は人事異動によりキャリア形成過程において一時期に販売業務に従事することはあっても、会社の判断によって他の現業業務、本社業務や配置転換などがあり得る。これに対して契約社員は就業場所の変更はあっても業務内容に変更はない。
注:正確には原告は契約社員 B であった者であり、これとは別に雇用期間の定めが異なる契約社員 A という職種が存在した。
- 3. 上記の点や、登用制度により契約社員 B から契約社員 A 、契約社員 A から正社員になる機会が与えられている点を踏まえると、賃金、各種手当、賞与、退職金、褒賞についての違いが不合理であるとはいえず、違法性はない。
<退職金の有無に関する会社側の主張>
正社員と契約社員との間には職務の内容や配置の変更の範囲等に明確な違いがあること、長期雇用を前提とする正社員に対する継続雇用に期待する功労や福利の要素、有用な人材の確保及び定着を図る目的等を踏まえると、契約社員についてのみ退職金制度を設けないことが不合理であるとはいえない。
ほぼ会社側の主張を認めた第 1 審 (東京地裁)
両者の主張に対して、第 1 審の東京地裁ではほぼ会社側の主張を認める判決が下されました。まず、労働契約法 20 条の適用に関して、改正法施行前の 2013 年 3 月 31 日以前の労働条件の違いには適用されないこと、また、条文が「不合理と認められるものであってはならない」と規定されており、「合理的でなければならない」という文言が用いられていないことから、労働条件の違いに合理的な理由があることまで要求する趣旨ではないという考え方が示されています。
そのうえで、正社員と契約社員の間では職務の内容及び配置の変更の範囲についても明らかな相違があるとし、さらに労働条件の比較対象は売店業務に従事する正社員に限定するのではなく広く社内の正社員一般とするのが相当であるとして、これを踏まえて各労働条件の違いが不合理であるかどうかについて、以下のような判断を示しました。
<不合理であるとはいえない労働条件の違い>
- ・本給及び資格手当の格差 (入社 10 年目で高卒新規採用の正社員の 82% ~ 87% 程度)
- ・住宅手当の有無 (正社員にのみ支給)
- ・賞与の格差 (入社 10 年目までの高卒新規採用の正社員が 50 万円前後であるのに対して契約社員は一律 12 万円)
- ・退職金の有無 (正社員にのみ支給)
- ・永年勤労の褒賞の有無 (正社員のみが対象)
<不合理な労働条件の違い>
- ・早出残業手当の割増率の違い (正社員は 27% ないし 35% であるのに対して契約社員は 25%)
結果としては、早出残業手当の割増率以外の違いについては退職金の有無も含めて不合理ではないとし、契約社員側の訴えはごく一部しか認められませんでした。地裁はその根拠として、職務の内容等の違いのほかに、長期雇用を前提とする正社員について有為な人材の確保・定着を図るためにより手厚く処遇することは企業の人事政策上の判断として一定の合理性があることを認めており、基本的には会社側の主張に沿った判決内容であったといえるでしょう。
会社側に退職金の支払いを命じた控訴審 (東京高裁)
これに対して、原告、被告の双方が控訴して争われた東京高裁での判決では原告 (契約社員側) の主張がより広く認められ、退職金についても正社員の 1/4 に相当する金額を支払うよう会社側に命じました。労働条件の比較対象に関しては、地裁では正社員全体としたところ、高裁では原告からの訴えに沿う形で売店業務に従事する正社員を比較対象とし (正社員全体を比較対象とすることは職務の内容が大幅に異なることから不合理性の判断が困難になるとの考え)、各労働条件の違いについて以下のような判断を示しました。
<不合理であるとはいえない労働条件の違い>
- ・本給及び資格手当の格差 (本給は販売業務に従事する正社員の 70% 台、資格手当は正社員のみに支給)
- ・賞与の格差 (正社員が過去 5 年平均で本給 2 ヶ月分プラス 17.6 万円であったのに対して契約社員は一律 12 万円)
<不合理な労働条件の違い>
- ・住宅手当の有無 (正社員にのみ支給)
- ・退職金の有無 (正社員にのみ支給)
- ・褒賞の有無 (正社員のみが対象)
- ・早出残業手当の割増率の違い (正社員は27%ないし35%であるのに対して契約社員は 25%)
本給及び資格手当の格差、賞与の格差については、根拠は第 1 審とは若干異なる部分もあるものの、結論としては第 1 審と同様に不合理であるとはいえないとした一方で、住宅手当については、主として従業員の住宅費を中心とした生活費を補助する趣旨であって職務の内容等によって差異が生ずるものではないことから、「有為な人材の確保・定着」という理由のみで支給対象を正社員に限るのは正当化できず、不合理な違いであると判断しました。
また退職金についても、一般論として長期雇用を前提とする無期契約労働者に対してのみ退職金制度を設けることについて人事政策上一概に不合理であるとはいえないとしつつ、訴えを起こした契約社員は 10 年前後の長期間にわたって勤務していた事実があること等を考慮すると、少なくとも長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分 (正社員の 1/4 に相当する額) すら支給しないことは不合理であるとしました。
さらに賠償すべき退職金の額の算定にあたっては、改正法施行前の 2013 年 3 月 31 日以前の勤続期間を通算して計算しており、改正法施行後の 2013 年 4 月 1 日以後の期間のみを計算の対象とした住宅手当や早出残業手当に関する賠償額の算定とは異なる取り扱いとなっています。その根拠は、契約社員に支給すべき退職金を、賃金の後払いではなく功労報償の性格を有する部分としたことによるものと考えられます。
そのほか、褒賞についても、支給の実態からすると業務の内容にかかわらず一定期間勤続した従業員を対象としたものとなっていることから、契約社員に対してこれを支給しないのは不合理であるとしました。
退職金制度を設けている企業に及ぼす影響
原告側は控訴審の判決内容はなお不当であるとして上告の意思を示していることから、最終的な結論については最高裁の判断を待つ必要がありそうですが、仮に今回の高裁の判決内容をもとに考えた場合、退職金制度を設けている企業には以下のように大きな影響が及ぶことが考えられます。
退職金制度は、そのほとんどが正社員のみを対象としているのが実態ですが、高裁の判決では「正社員は長期雇用を前提としているから」「有為な人材の確保・定着という人事政策上の必要性があるから」という理由だけで長期間にわたって勤務した非正規社員に退職金を一切支給しないのは不合理であるということが示されました。
2013 年 4 月に施行された労働契約法の改正ではいわゆる「無期転換ルール」が定められ、2018 年 4 月からはこのルールに基づく無期転換への申し込みが可能となったことから、無期転換社員に対する退職金や企業年金の扱いが問題となっていますが、今回の判決に従えば、たとえ有期雇用契約のままであったとしても退職金を支給しなければならないことになります。
その際、支給すべき金額については今回の判決では「少なくとも正社員の 1/4 相当」とされましたが、割合を 1/4 とした根拠については明確に示されていません。今回のケースでは退職金の給付設計が最終給与比例であったことから、同様の給付設計である退職金については 1/4 というのが 1 つの目安になるのかもしれませんが、例えば定年退職者に対して一律に支給される定年加算金等がある場合には、功労報償の性格が強いものであるとして、より高い割合での支給を求められる可能性があると考えます。
一方でポイント制のような積み上げ型の退職金制度においては、賃金の後払いとしての性格を重視するという考え方もとり得ます。その場合、例えば勤続ポイント等に相当する額の全部または一部については職務の内容によらず支給すべきものとして、改正法施行後の 2013 年 4 月 1 日以降の累積分に対して支払うという判断もあり得るでしょう。
確定拠出年金を実施している企業に及ぼす影響
また、確定拠出年金を退職金制度として実施している企業 (もしくは退職金制度の一部が確定拠出年金で構成されている企業の確定拠出年金部分) においては、非正規社員を加入対象外としていたり、加入対象としている場合でも確定拠出年金の掛金額の水準に不合理な格差があるときには問題となる可能性があります。
例えば、正社員に対する掛金を基本給の一定割合と定めている場合には、非正規社員にも同じ割合で掛金を拠出することが求められるでしょうし、掛金のうち勤続年数に応じて固定的に拠出される部分がある場合には、当該部分については非正規社員にも拠出するように求められる可能性があります。2013 年 4 月 1 日以降本来掛金として拠出するべきであった金額のうち、拠出されなかった部分の累積額については、利息を加味したうえで退職時に支給するよう求められる可能性も否定できません。
なお、確定拠出年金制度においては法律上、60 歳未満の厚生年金被保険者全員を加入者とすることが原則とされており、別途加入資格を定める場合には、加入者とならない者に対して確定拠出年金の掛金に相当する額を賃金に上乗せして支給する等の代替措置を設けることとされています (但しパート社員等で著しく労働条件が異なる者については例外的に代替措置を設ける必要はないとされている)。この規定に沿って (注) 、非正規社員に対して手当等の形で掛金に見合う金額が賃金として支給されている場合には、確定拠出年金の加入対象外としていたとしてもその違いは不合理ではないといえるでしょう。
注:確定拠出年金法では、短時間労働者等で厚生年金の適用対象でない者についてはそもそも企業型確定拠出年金の加入対象から外されているが、労働契約法 20 条においては厚生年金の適用対象であるかどうかの区別はない点に留意する必要がある。
著者 : 向井洋平 (むかい ようへい)

クミタテル株式会社 代表取締役社長
1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004 年にIICパートナーズ入社。2020年7月、クミタテル株式会社設立とともに代表取締役に就任。大企業から中小企業まで、業種を問わず退職金制度や高年齢者雇用に関する数多くのコンサルティングを手掛ける。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー、2級FP技能士。「人事実務」「人事マネジメント」「エルダー」「企業年金」「金融ジャーナル」「東洋経済」等で執筆。著書として『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。
出口 (イグジット) を見据えたシニア雇用体制の確立をしましょう
労働力人口の減少と高齢化が同時進行する中、雇用の入口にあたる採用、入社後の人材育成・開発に加え、出口 (イグジット) をどうマネジメントしていくかが、多くの企業にとっての課題となりつつあります。特に、バブル入社世代が続々と 60 歳を迎える 2020 年代後半に向けて、シニアの雇用をどう継続し、戦力として活用していくのか、あるいはいかに人材の代謝を促進するのか、速やかに自社における方針を策定し、施策を実行していくことが求められます。多くの日本企業における共通課題であるイグジットマネジメントの巧拙が、今後の企業の競争力を左右するといっても過言ではありません。
シニア社員を「遊休人員化」させることなく「出口」へと導くイグジットマネジメントを進めるために、まずは現状分析をおすすめします。