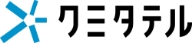企業型確定拠出年金の加入者への投資教育 DC Education
企業型確定拠出年金(DC)では加入者本人が自己責任により運用方法を選択することから、その選択が適切に行われるよう、加入者に対する投資教育の実施も、事業主の努力義務として定められています。 投資教育は、従業員が加入者となるとき(DCの導入時を含む)に加え、加入者となった後も継続的に実施することが求められています。 投資教育に盛り込むべき内容は下記のとおり多岐にわたっており、対象者の属性(年齢層や制度に対する関心・理解度)に応じたテーマの選定や、計画的な実施が求められます。
目次
投資教育の内容
確定拠出年金制度等の具体的な内容
1. 日本の年金制度の概要、改正等の動向及び年金制度における確定拠出年金の位置づけ
2. 確定拠出年金制度の概要
・制度に加入できる者とその拠出限度額
・運用方法
・給付の種類、受給要件
・離転職した場合の資産の移換方法
・拠出、運用及び給付の各段階における税制措置
等
金融商品の仕組みと特徴
預貯金、保険商品、投資信託等それぞれの金融商品についての次の事項
- その性格又は特徴
- その種類
- 期待できるリターン
- 考えられるリスク
- 投資信託については価格に影響を与える要因等
資産の運用の基礎知識
- 資産の運用を行うに当たっての留意点
- リスクの種類と内容
- リスクとリターンの関係
- 長期運用の考え方とその効果
- 年齢、資産等の属性によりふさわしい運用の方法のあり方は異なり得るため一律に決まるものではないが、長期的な年金運用の観点からは分散投資効果が見込まれるような運用の方法が有用である場合が少なくないこと
確定拠出年金制度を含めた老後の生活設計
- 資産形成は現役時代から取り組むことの必要性
- 自身が確保しなければならない費用の考え方
- 確定拠出年金や退職金等を含めた老後の資産形成の計画や運用目標の考え方
- 運用リスクの度合いに応じた資産配分例の提示
- 離転職の際には正規の手続きにより資産を移換し、運用を継続していくことが重要であること
最後の、離転職の際の資産移換手続きに関する項目が定められている背景には、いわゆる自動移換者の問題があります。
離転職により、運用指図者となることなく加入者資格を喪失した者は、転職先のDCまたは個人型確定拠出年金(iDeCo)等に資産を移換する手続きを行う必要がありますが、そうした手続きが行われないまま6ヶ月が経過すると、資産は自動的に国民年金基金連合会に移換されることとなります。自動移換された資産は運用されることなく留め置かれ、そのままでは60歳になっても給付を請求することもできません。
自動移換者は年々増加しており、自動移換された資産が将来的に未払いとなってしまう可能性も懸念されています。