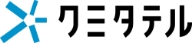企業型確定拠出年金の設計 DC Design
企業型確定拠出年金(DC)の設計は、法令に基づき、実施企業ごとに決定していきます。以下の内容は2024年12月現在施行されている法令に基づいています。
企業型確定拠出年金の加入資格
企業型確定拠出年金(DC)を実施する際には、実施事業所に使用される厚生年金被保険者全員を加入者とする(掛金の拠出対象とする)のが原則ですが、以下に掲げる「一定の資格」を満たす者を加入者とすることも認められています。
- 一定の職種(研究職、営業職、事務職などの労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにおいて規定される職種)に属する者
- 一定の勤続年数以上(または未満)の者
- 「60歳以上の一定の年齢」未満である者(但し、新たにDCを実施するとき及び新たに加入者となる場合には「50歳以上の一定の年齢」未満とすることが可能)
- 希望する者(一度加入した者は任意に加入者資格を喪失することはできない)
なお、上記のような加入者資格を定める場合には、「60歳以上の一定の年齢」に到達したことにより加入者資格を喪失した場合を除き、DCの加入者とならない者について代替措置(前払いを含む他の退職給付制度)を講じる必要があります。ただし、嘱託社員やパート社員等、労働条件が著しく異なる者については、必ずしも代替措置を講じる必要はないとされています。
実際には、通常の退職金制度と同様に正社員のみをDCの加入者としている企業が多くなっていますが、その場合、正社員以外の従業員(60歳未満の厚生年金被保険者)に対しては、代替措置を講じるか、「労働条件が著しく異なる」ことを示す必要があります。
企業型確定拠出年金の加入資格の喪失
加入者は、厚生年金被保険者でなくなったとき、資格喪失年齢に達したとき、その他退職や死亡等により加入者資格を満たさなくなったときに加入者資格を喪失し、掛金の拠出対象ではなくなります。
60歳以降に退職等により加入者資格を喪失した者は、資産の運用のみを行う運用指図者となり、老齢給付金の支給要件を満たしたときに給付を受け取ることができます。また、加入者であった者で障害給付金の受給権がある者も、自社のDCの運用指図者となります。
一方で、60歳未満で加入者資格を喪失した者については、障害給付金の受給権がある場合や死亡の場合を除き、原則として他の企業のDCまたは個人型確定拠出年金(iDeCo)に資産を移換することとなります。
企業型確定拠出年金の事業主掛金の設定
企業型確定拠出年金(DC)の加入者には会社が拠出する「事業主掛金」を必ず設定する必要があります(0円は不可)。事業主掛金の算定方法は以下のいずれかの方法により定めることとなります。
- 定額(全加入者同一の掛金額)
- 給与の一定率(全加入者同一の掛金率)
- 定額と給与の一定率の合計
なお、給与の一定率については、原則として給与規程や退職金規程等に定められたものを用いることとされており、退職金ポイント等、DCのために別途定めた給与を用いることも可能です。実際、多くの企業では給与の一定率の方法により事業主掛金を設定しています。
また、DCの掛金(事業主掛金と、後述する加入者掛金の合計額)には以下のように上限(拠出限度額)が定められており、算定された事業主掛金がこれを超過する場合には、超過分を他の退職給付制度(前払いを含む)で支給する等の対応が必要となります。
【DB等の加入者】
55,000円-他制度掛金相当額(DB等の制度ごとに計算)
但し、2024年12月以前からDCを実施している場合は経過措置として従前の規約に基づく掛金の拠出が可能(拠出限度額27,500円)。2024年12月以降、DB等の給付設計やDCの掛金設計を変更した時点で経過措置の適用は終了。
【上記以外】
55,000円
DCの掛金は原則として毎月拠出します(当月分の掛金を、翌月末までに資産管理機関に納付)。あらかじめ定めた月に2ヶ月分以上をまとめて拠出することも可能ですが、事業主掛金を毎月拠出以外の方法で拠出している例はほとんどありません。
事業主は、各加入者に対して継続して掛金を拠出しなければなりませんが、給与が支払われない休職等の期間については、例外的に掛金の拠出を中断する期間として定めることができます。
なお、各事業年度に支出した事業主掛金はその全額が損金に算入され、掛金の拠出時点では個人(従業員)の所得にもなりません。
企業型確定拠出年金の事業主掛金の返還
企業型確定拠出年金(DC)では一度拠出された掛金は加入者個人の口座で管理され、懲戒解雇のような場合も含めて後から減額されることはありません。
しかし、勤続3年未満で退職したことにより加入者資格を喪失した従業員に対しては、事業主掛金に相当する額を返還させる規定を設けることができます(死亡や資格喪失年齢に達したことにより加入者資格を喪失した者は対象外)。
返還の対象となる勤続年数を3年未満より短い期間で設定したり、返還すべき退職事由を懲戒解雇や自己都合退職等に限定することも可能です。
事業主への返還額は原則として事業主掛金の総額となりますが、運用損失により資産額が事業主掛金の総額を下回っている場合は資産額が返還額となります。
また、資産額に事業主掛金以外を原資とする部分(具体的には加入者掛金や他制度からの移換金)が含まれている場合、返還の対象となるのは事業主掛金を原資とする部分に限定されるため、当該部分の按分方法をあらかじめ定めておく必要があります。
企業型確定拠出年金の加入者掛金(マッチング拠出)の設定
企業型確定拠出年金(DC)の掛金は事業主が拠出しますが、加入者が給与天引きにより掛金(加入者掛金)を拠出し、事業主掛金に上乗せできる仕組みが用意されています。この仕組みは一般に「マッチング拠出」と呼ばれています。
マッチング拠出を導入するかどうかは各企業ごとに決定し、導入する場合は加入者掛金の額を設定します。加入者掛金は具体的な金額により複数設定し、例えば「1,000円以上1,000円単位の任意の額」のように、各加入者が拠出可能な最大の範囲で設定するよう努めることとされています。
マッチング拠出が導入された場合にも加入者掛金を拠出するかどうか、及び加入者掛金としていくらを選択するかは各加入者の任意であり、加入者掛金の拠出を停止したり、再開することも可能です。また、加入者の意思による加入者掛金の額の変更は年に1回のみ行うことが認められています。
ただし加入者掛金の選択にあたっては以下の条件をいずれも満たす必要があり、事業主掛金がDC掛金の拠出限度額に達している場合には、加入者掛金を拠出することはできません。
- 加入者掛金は事業主掛金以下であること
- 事業主掛金と合計して拠出限度額を超えないこと
(注)事業主掛金が変更されたことにより加入者掛金の変更が必要となった場合の変更は、加入者の意思による年1回の変更にはカウントされない。
また、事業主掛金を毎月拠出以外の方法により拠出している例はほとんどありませんが、加入者掛金については賞与の月などにまとめて拠出できるようにしている企業も一部にあります。
企業型確定拠出年金(DC)の加入者掛金は税制上、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、拠出額の全額が本人の所得から控除されます。マッチング拠出は、所得税・住民税の優遇措置を設けることで、本人の自助努力による老後に向けた資産形成を支援するための仕組みと位置付けられます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)との併用
企業型確定拠出年金(DC)において加入者本人が掛金を拠出できるようにする仕組みとして、マッチング拠出のほかに個人型確定拠出年金(iDeCo)との併用があります(DCの事業主掛金が毎月拠出でない場合はiDeCoの併用は不可)。
従業員は以下の拠出限度額の範囲内で自由にiDeCoの掛金額を設定することができ、マッチング拠出のように事業主掛金以下でなければならないという制約はありませんが、iDeCoの掛金額は月5,000円以上とする必要があります。なお、マッチング拠出とiDeCoを併用することはできません。
【DB等の加入者】
「55,000円-他制度掛金相当額-DC事業主掛金」以内、かつ20,000円以内
【上記以外】
「55,000円-DC事業主掛金」以内、かつ20,000円以内
本人がiDeCoに拠出した掛金は、マッチング拠出の加入者掛金と同様に小規模企業共済等掛金控除の対象となり、拠出額の全額が所得から控除されます。
他制度からの資産等の移換
企業型確定拠出年金(DC)実施企業において、入社等により新たに加入者となった従業員が以前に他社のDCやその他の企業年金制度等に加入しており、その資産等を自社のDCに移換することを申し出た場合には、移換金を受け入れることとなります。具体的には以下のような資産や給付が移換の対象となります。
- 以前の会社で積み立てたDCの資産
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)で積み立てた資産
- 以前の会社で加入していた確定給付企業年金または厚生年金基金の脱退一時金相当額
- 以前に企業年金連合会に脱退一時金等を移換し、通算企業年金の原資となっている積立金
また、DC実施企業において他の退職金制度等の改定(他制度からDCへの移行)を行った場合には、以下のように他制度で積み立てた資産等をDCに移換することができます。
制度改定に伴うDCへの移換可能額
| 移行前の制度 | 移換可能額 |
| 退職一時金制度 | 移行前後の自己都合退職金額の差額(注1) |
| 確定給付企業年金及び厚生年金基金制度 | 移行前後の最低積立基準額の差額(制度終了の場合は残余財産の分配額) |
| 中小企業退職金共済制度(中退共) | 解約手当金相当額(注2) |
注 1:移換が終了するまでの期間に応じた利子相当額を加えることができる。
注 2:中小企業でなくなった場合、及びDCを実施する企業と合併等を行った場合に限り、退職金共済契約を解除してDCに資産を移換することが可能。
確定給付企業年金、厚生年金基金及び中小企業退職金共済からの移換については一括で行われ、確定給付企業年金及び厚生年金基金に積立不足がある場合には、そのうち移行割合に応じた額を制度移行時に一括拠出する必要があります。
一方、退職一時金からの移換については、制度移行を行う年度を含めて4~8年度の範囲で各年度に均等に分割して移換することとなります。
なお、積立不足のある確定給付企業年金及び厚生年金基金からの移行に伴う一括拠出掛金や、退職一時金からの各年度の移換金の支出は、その全額が損金に算入されます。
また、資産の移換時点では、移換金は個人(従業員)の所得にもなりません。
給付の種類と支給方法
DCの中心的な給付は60歳以降に受け取る老齢給付金ですが、そのほかに障害給付金、遺族給付金、脱退一時金の各給付があります。これらの給付の支給要件は下記のとおりです。
DCの給付の種類と支給要件
| 給付の種類 | 支給要件 |
| 老齢給付金 |
・8年以上10年未満:61歳 |
| 障害給付金 |
・障害基礎年金の受給者 |
| 死亡一時金 |
|
| 脱退一時金 |
【個人別管理資産が15,000円以下のとき】 |
上記のとおり、老齢給付金は60歳に受給可能となり、年金、一時金、またはこれらの組み合わせにより受け取ることができます(法律上は年金での支給が原則であるが、通常は一時金での支給を選択できるようにしている)。
老齢給付金の支給方法
| 支給方法 | 給付の内容 |
| 年金(分割取崩) |
|
| 年金(年金商品の購入) |
|
| 一時金 |
|
給付の支払いは本人からの請求に基づいて行われ、最長75歳になるまでは給付を請求せずに(資金を引き出さずに)運用を続けることができます。75歳になると自動的に裁定が行われ、あらかじめ定めた方法(通常は一時金)により給付が支払われます。なお、それぞれの給付に対する課税の内容は下記のとおりとなっています。
DCの給付に対する課税
| 給付の種類 | 課税の内容 |
| 老齢給付金(年金支給) | 雑所得として課税。公的年金等控除の対象となる。 |
| 老齢給付金(一時金支給) | 退職所得として課税。退職所得控除が適用される。 |
| 障害給付金 | 非課税 |
| 死亡一時金 | 相続税として課税。ただし法定相続人1人当たり500万円までは非課税となる。 |
| 脱退一時金 | 一時所得として課税。 |